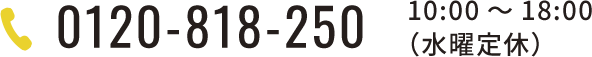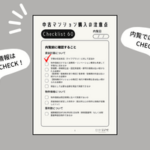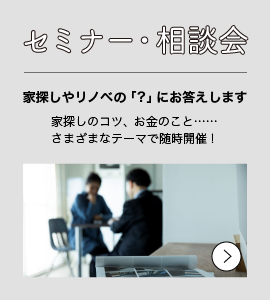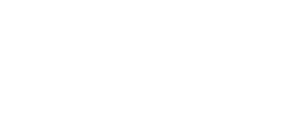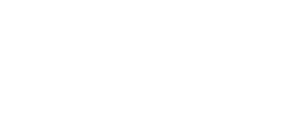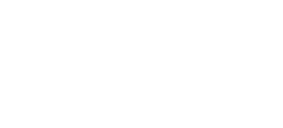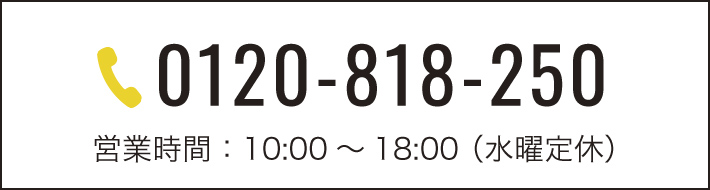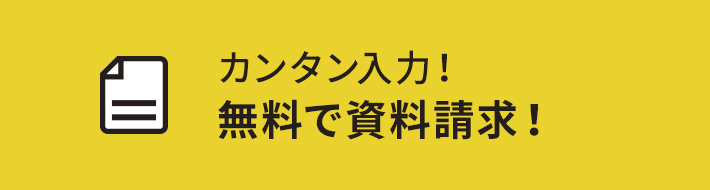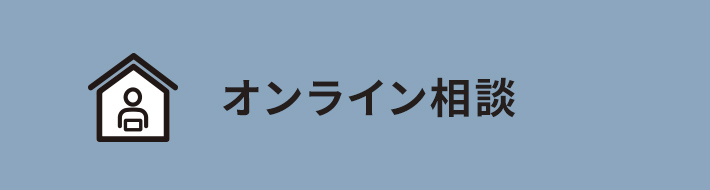中古マンションを購入するときは、売買契約、住宅ローンの申し込み、決済・引き渡しなど、入居までの間にいくつかの手続きがあります。
事前に必要書類を揃えたり、手付金など現金を用意したり。
それらをスムーズに進めるために、当日の手続きや必要な準備を押さえておきましょう。
この記事では「売買契約」「住宅ローンの申し込み」「決済・引き渡し」の3つ手続きにフォーカスして、当日の流れや必要書類についてまとめました。
これから住宅購入を計画されている方は、ぜひこの記事をチェックリストとしてお役立てください。
目次
中古マンションの購入の流れ
中古マンションの購入は、大きく分けて8つのステップで進行します。
中古マンション購入の8ステップ
- STEP1. 資金計画
- STEP2. 不動産仲介会社・リノベーション会社探し
- STEP3. 物件探し
- STEP4. 物件の内見
- STEP5. 購入申し込み
- STEP6. 売買契約
- STEP7. 住宅ローン審査と金消契約
- STEP8. 決済・物件引き渡し
煩雑な手続きが発生するのは、このうち「STEP6. 売買契約」「STEP7. 住宅ローン審査と金消契約」「STEP8. 決済・物件引き渡し」の三点です。
それぞれどんな手続きを行うのか、必要書類、注意すべきポイントを個別に見ていきましょう。
売買契約の手続きと必要書類
売買契約は、買いたい物件が決まり、購入申込が受け入れられたら、通常1~2週間のあいだに締結します。
当日の手続きと必要書類は以下の通りです。
売買契約当日に行う手続き
- 物件の重要事項説明
- 売買契約の締結
- 手付金の支払い
必要書類・用意するもの
- 印鑑(実印)
- 本人確認書類
- 手付金
- 印紙代(5000万円以下なら1万円)
契約当日は、売主と買主が不動産会社の事務所等で対面し、重要事項説明を受けたうえで、売買契約書に署名・捺印をして契約が成立します。
(重要事項説明には売主は同席せず、説明を受けるのは買主のみ、というケースも)
この時、買主は売主に手付金を支払います。
手付金として入れるべき金額はとくに決まっていませんが、物件価格の10%前後を手付として入れる方が多いようです。中古マンションの場合、ちょうど諸費用相当額にあたります。
現金での支払いとなりますので、当日までに準備をお忘れなく。
ここでのポイントは、売買契約を結ぶ前に、重要事項説明書と契約書の内容を確認しておくこと。
とくに「売主の契約不適合責任(旧名称:瑕疵担保責任)」と「住宅ローンの特約」は、よくチェックしておきましょう。
契約不適合責任
引き渡し後に物件の瑕疵(雨漏り・白アリ被害など)が見つかった場合、売主は修繕する責任を負います。これを売主の契約不適合責任といいます。
とくに売主が不動産業者の場合は、「最低2年、契約不適合責任を負う」と法律で定められています。
しかし、売主が個人の場合は「引き渡しから3ヶ月間、契約不適合責任を負う」というように期間を短縮したり、あるいは「契約不適合責任を負わない」ということも認められています。
個人の自宅を売却する場合、住んでいる間に内装や設備が劣化していることはある程度予測できます。その責任を「前居住者に負わせるのは酷である」と考えるためです。
したがって個人売主から物件を購入した場合、もし引き渡し後に給排水管の漏水・雨漏りなどが見つかっても、基本的には買主が修繕することになります。
中古マンションはリフォームやリノベーションを前提に購入される方が多いので、問題になるケースはごく稀ですが、既存の設備や配管配線の再利用を考えている方は、「もし故障や傷みがあった場合も、修繕費用は自己負担」ということを覚えておきましょう。
住宅ローン特約
あなたがもし住宅ローン本審査に落ちた場合、「契約は無効」とする特約です。
前提として、売買契約を結んだあと、自己都合で契約を白紙にすることはできません。キャンセル料として手付金が徴収されます。
しかし、住宅ローン本審査に落ちた場合に限り、手付金は全額返ってくるというのが、この特約です。
事前審査を受けているとはいえ、最終的な合否は本審査の結果が出るまでわかりません。万一の場合に備え、契約書にこの旨明記されていることを確認してください。
できれば契約日より前に書類の写しをもらい、疑問点は契約日までに不動産業者に確認しておくと安心です。
住宅ローンの申し込み手続きと必要書類
売買契約を締結したら、すぐ住宅ローンの申し込み手続きを行います。
住宅ローンを借りるには、審査を受ける必要があります。
審査では、年収と借入額のバランス、マイカーローンなど住宅ローン以外の借入の有無、個人信用情報など「貸したお金をきちんと返せるのか」を主軸に調べられます。
また、返済中にもしものことがあった場合に備え、団信(団体信用生命保険)への加入を義務付けている金融機関が多いです。
団信に加入するためには、通常の生命保険と同様「健康状態に問題がないか」の告知を行う必要があります。
さらに、物件の担保価値も審査の対象となります。途中でローンを払えなくなった場合に備え、売却して残債を回収できるかをチェックされるのです。
これらの審査は、「事前審査」と「本審査」の二段階で行われます。
事前審査は、ローンが組めるかどうかを確認するためのもの。その名のとおり本申し込みの前に行うもので、通常は物件探しと並行して審査を受けるケースが多いです。
本審査は、売買契約の成立後に行います。普通「住宅ローンの申し込み」といえば、この本審査のことを指します。
審査手続きは、書類を出してしまえばあとは待つだけ。審査には次のような書類が必要です。
| 書類の名称 | 入手先 |
| 源泉徴収票(自営業の場合は確定申告書) | 勤務先 |
| 売買契約書 | 不動産会社 |
| 重要事項説明書 | |
| 物件の資料(チラシやパンフレット、図面など) | |
| 登記簿謄本 | 市区町村役場 |
| 印鑑証明書 | |
| 住民票 | |
| 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証) 課税証明書(住民税決定通知書) |
書類の提出後、本審査の結果がわかるまでは、早くて1〜2週間、長ければ1ヶ月くらいかかります。
審査に通ったら、「金銭消費貸借契約」を結びます。そして融資実行の日が決まったら、決済・引き渡しと進んでいきます。
なお、住宅ローンを利用せず、現金で一括購入したいとお考えの方もいるかもしれません。
現金一括購入の場合、住宅ローンに関する手続きは一切不要。売買契約の締結後、決裁・引き渡しへと進みます。
ローン審査については、下記により詳しい特集記事がありますので、よろしければ併せてご覧ください。
決済・引き渡しの手続きと必要書類
住宅ローンの審査に通って金銭消費貸借契約を結んだら、融資実行の日に合わせ、決済・引き渡しの手続きを行います。
当日の手続きと必要書類は以下の通りです。
決済当日に行う手続き
- 登記手続きの委任
- 融資の実行
- 売買代金の支払い
- 諸費用の支払い
- 固定資産税・管理費・修繕積立金の精算
- 管理規約・住宅設備の取扱説明書など関係書類の受け取り
- 鍵の受け取り
必要書類・用意するもの
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 通帳・届出印・キャッシュカード(ローンを組んだ金融機関のもの)
- 売買代金(手付金額を差し引いた分)
- 諸費用(仲介手数料・登記費用など)
- 固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金の精算金
決裁・引き渡しの手続きには、売主・買主・不動産業者の他、金融機関のローン担当者、登記をおこなう司法書士も同席します。
決済の大部分は実行された融資から支払われますが、一部、売買契約の際の手付金のように現金での支払いも発生します。
たとえば、年の途中で物件を売買した場合、その物件にかかる固定資産税・都市計画税を日割りで精算する必要があります。管理費・修繕積立金も、月の途中で物件を売買した場合は同様に、日割りで精算します。
また登録免許税や司法書士への報酬、不動産取得税、融資手数料や住宅ローンの保証料、火災保険料、仲介手数料などの諸費用も、ここで支払います。
諸費用の金額は、前述のとおり、中古マンションでは物件価格の10%程度。住宅ローンに組み込むこともできますが、実際には諸費用は現金で支払うという人が多いです。売買契約時に手付金として諸費用相当額を入れてある場合、そのお金をそのまま充当します。
登記手続きの委任
決済・引き渡し時におこなう項目の中に、登記手続きの委任があります。
売主・買主ともに、司法書士に登記書類を提出し、専門家でないと難しい登記手続きを代行してもらうというものです。
マンションの売買時に必要な登記は「所有権移転登記」と「抵当権設定登記(※住宅ローンを利用する場合)」の2つ。
司法書士は、決済・引き渡しの完了後(通常は当日中)に登記申請を行います。
買主は、住民票(金銭消費貸借契約時に提出したもの)と本人確認書類を用意すればOK。
司法書士が登記手続きを完了すると、物件は名実ともにあなたのものになります。
おわりに
不動産購入の手続きは煩雑で、当日はなにを行うのか、用意すべき必要書類、注意すべきポイントなど、勝手がわからず不安に思われる方も少なくないのではないでしょうか。
ぜひこの記事を契約前に見返して、必要書類のチェック等にお役立てください。
当社ひかリノベは、物件探しからリノベーションの設計・施工までワンストップのリノベーション会社です。宅建資格をもつコーディネーター、建築士資格をもつデザイナー、施工管理の専任スタッフが社内に在籍し、家探しからリノベーション設計・施工まで完全内製でご提供しております。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードバナーより、どうぞお気軽にご覧ください。