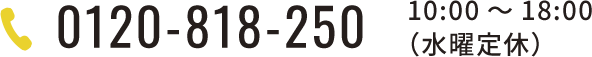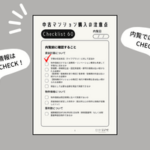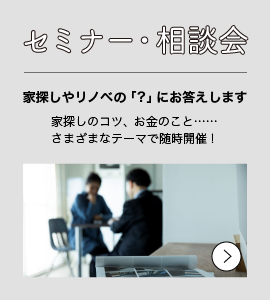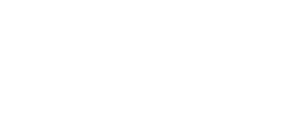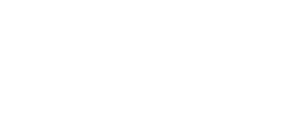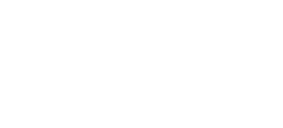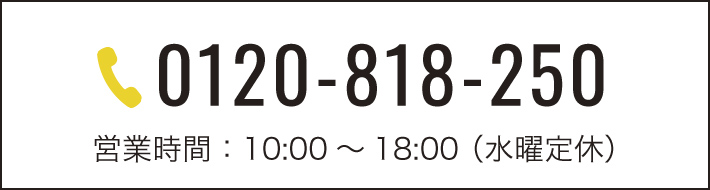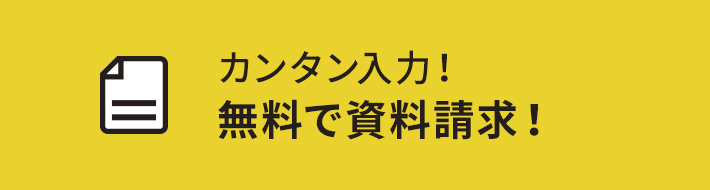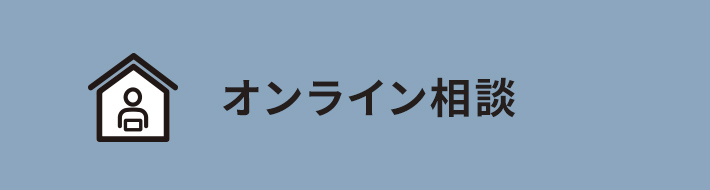住宅ローンは申し込めば誰でも利用できる訳ではありません。融資を受けるには、金融機関(銀行など)の審査をクリアする必要があります。
審査結果によっては、融資を受けることができず、住宅購入を諦めなくてはならない可能性も出てきます。住宅は高価な買い物であるうえに、返済期間も最長35年と長いので、必然的に貸す側もシビアにならざるを得ないのです。
今回の記事では、住宅ローンの審査項目と合格基準、さらに審査に落ちてしまった場合の対策について解説します。
これからローンを申し込む方、事前審査に落ちてしまったという方も、ぜひこの記事を参考になさってくださいね。
目次
住宅ローン審査の概要
住宅ローンの審査は、「事前審査」と「本審査」の二段階で実施されます。
事前審査を通過していても、本審査までに転職した・新たな借入を行ったなど状況が変わった場合、本審査で結果が変わる可能性があります。
事前審査とは、物件購入の事前に融資の目途を立てるための審査です。
購入したいと思える物件が出てきたら、そのタイミングで事前審査を申し込みます。
事前審査では、年収や借入の有無、勤務先・勤務形態・勤続年数、購入予定の物件の担保価値などがチェックされ、「返済能力があるかどうか」が判断されます。
事前審査の結果が出るまでの期間は通常、数日〜1週間です(金融機関によって差があります)
事前審査の承認後、本審査がおこなわれます。
本審査を申し込むタイミングは、不動産売買契約を結んだあと。この申込をもって、正式な融資の申込となります。
本審査では、本人の健康状態(多くの銀行では団体信用生命保険への加入を融資の条件としているため)、購入物件の担保価値、年収と返済負担率などがより詳細に確認されます。
本審査の結果が出るまでの期間は、早い場合で1〜2週間、長いと1ヶ月程度かかる金融機関もあります。
審査項目と審査基準~審査に通らない理由とは?
審査に落ちてしまう人は、具体的に何が原因なのでしょうか?
国交省が毎年発表している「民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書」によれば、融資を行う際に考慮する項目として、多くの金融機関が次の8つの項目を挙げています。
- 完済時年齢(99.1%)
- 健康状態(98.2%)
- 担保評価(98.2%)
- 借入時年齢(97.8%)
- 年収(95.7%)
- 勤続年数(95.3%)
- 連帯保証(95.1%)
- 返済負担率(92.1%)
年収と返済比率
審査に落ちる原因としてよくあるのが、年収に対して借入額が多すぎるパターンです。
住宅ローン審査では、「利息を含めた年間返済額が年収に占める割合(返済比率、返済負担率)」が重要視されます。
合格ラインは金融機関によって異なりますが、おおむね30%〜35%以下であれば問題ありません。
利息(金利)は「審査金利」といって、実際の実行金利よりも高めの3%〜4%で計算されます。
(※主要都市銀行の場合。金融機関によって計算方法や合格基準は異なります。例えばフラット35では、審査自の実行金利を審査金利としています)
この基準にしたがって融資限度額を算出すると、おおよそ下表の金額となります。
| 年収 | 借入可能額(元金) |
| 300万円 | 1,693万円 |
| 400万円 | 2,634万円 |
| 500万円 | 3,293万円 |
| 600万円 | 3,952万円 |
| 700万円 | 4,611万円 |
| 800万円 | 5,269万円 |
| 900万円 | 5,928万円 |
| 1,000万円 | 6,587万円 |
| 1,100万円 | 7,245万円 |
| 1,200万円 | 7,904万円 |
※フラット35「ローンシュミレーション」を使用して算出
返済比率は、車のローンや奨学金・消費者金融の利用・カードキャッシングなど住宅ローン以外の借入の残高も含めて計算されます。スマートフォンの端末代金を分割で支払っている人も多いと思いますが、これも借入として扱われるため、注意が必要です。
住宅ローン審査における年収と返済比率については、下記の特集記事があります。よろしければこちらも併せてご覧ください。
年齢
金融機関や商品にもよりますが、多くの銀行では完済時の年齢の上限を80歳としています。
35年ローンだとすると、借入時の年齢は44歳が上限になります。
さらに、会社員には定年退職があります。安定した収入があるうちに完済する方が望ましいので、40歳以上になると審査はやや厳しくなるようです。
勤続年数と雇用形態
かつては勤続年数2年以上を条件とする金融機関が多数派でしたが、近年は転職が珍しくなくなった現状からか、条件を緩和する銀行が増えてきました。例えば「キャリアアップのための転職なら勤続1年未満でもOK」という銀行もあります。
ですが、全体としては、やはり勤続年数が長い方が安定していると判断される傾向に変わりはありません。転職のタイミングに関しては、慎重に対応したいところです。
雇用形態については、契約社員やパートだからといって必ずしも融資がNGという訳ではありませんが、やはり固定給で毎月安定した収入のある正社員の方が有利になる傾向です。
フリーランスや自営業で生計を立てている個人事業主の場合は、直近3年分の所得(収入ではなく、経費を除いた金額)が黒字であることが条件です。
健康状態
ほとんどの銀行では、団体信用生命保険(団信)への加入を融資の条件としています。万が一のとき、団信の保険金が残額の返済に充てられることになります。
団信は生命保険であるため、加入にあたっては既往症や病歴の有無を告知しなくてはなりません。もし病気を理由として加入できないと、ローンを組むこともできなくなります。
ただし、フラット35のように、団信加入を任意としている商品もあります。健康に不安がある方は、こうした商品を検討すると良いでしょう。
団信の告知事項については、下記に特集記事があります。よろしければこちらも併せてご覧ください。
担保評価
もしローンを途中で返済できなくなった場合、銀行は物件(土地や建物)を売却してお金を回収します。つまり住宅ローンでは、物件を担保にするわけです。
物件の担保としての価値は、築年数や周辺の相場を踏まえて算定されます。銀行はその価値以上に融資をすることはありません。担保価値が無い/低いと判断された場合は、「融資をしない」または「融資金額を下げる」という対応がなされます。
中古物件、とくに築年数の古い建物は、担保評価も低くなりがちです。もっとも築古物件は概して販売価格も安価であるため、担保価値とそれほど大きなギャップが生じるケースは稀でしょう。
信用情報
マイカーローンや学資ローン等の借入や支払いの状況、クレジットカードの利用履歴などを「信用情報」といいます。信用情報の対象となる範囲は広く、学資ローンやマイカーローンなどの融資はもちろん、クレジットカード、キャッシング、奨学金、スマートフォン等の端末代金の割賦、さらにアパートの家賃も保証会社と契約を結んで支払いを行っている場合は対象となります。
金融機関はこれらの支払延滞の有無を厳しくチェックします。支払いや引き落としが61日以上遅延すると、信用情報に「異動」と記載されます。異動の記録がつくと、どの金融機関でもローン審査の結果は厳しいものとなります。
事前審査と本審査の間に滞納してしまった場合も、本審査の結果に影響する恐れがあります。
個人信用情報は、割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC)・日本信用情報機構(JICC)・全国銀行協会(KSC)の各機関が記録しています。不安な方は審査を受ける前に、ご自身の信用情報を取り寄せて調べておくことをおすすめします。
「事前審査に通ったのに本審査で落ちる」場合も
事前審査で申告した内容に誤りがあったり、本審査までの間に収入や借入の額が変わったりすると、本審査で結果が変わる可能性があります。審査が完了するまで、新たにマイカーローン等を組んだり、キャッシングや消費者金融を利用したりすることは避けましょう。
また、事前審査と本審査の間に転職をした場合も、勤続年数の基準を満たせなくなる可能性があります。
最近はインターネットで事前審査ができる金融機関も増えていますが、オンライン審査では源泉徴収票などをチェックしないことが多く、それゆえに「事前審査は通過したが、本審査を通過できない」というケースも少なくないようです。また、みずほ銀行のように事前審査はAI簡易審査という場合もあり、こちらも本審査で結果が変わる可能性があります。
審査に落ちた場合の対策
ひとつの銀行で審査に落ちたからといって、住宅購入をただちに諦めることはありません。ここでは、審査に通らなかった場合の対策をご紹介します。
自己資金を増やす
返済比率(年収に対して借入額が多すぎる)が原因で満額融資を受けられなかった場合は、借入額を減らすか、年収を増やすかのいずれかの対応が必要です。
借入額を減らす方法として考えられるのは、「自己資金を投入する」ことでしょう。つまり頭金を増やすということです。
親から資金の援助を受けられる場合は、住宅取得資金贈与の非課税特例を利用することができます。住宅購入のための親から子への資金援助は、省エネ住宅の場合は1,000万円まで/一般住宅の場合も500万円までは贈与税はかからないという制度です。2023年12月31日までの制度なので、利用をお考えの方はお早めに。
ペアローン・収入合算
借入額はそのままに、年収を増やして審査に通るようにしたい場合は、自分一人ではなく夫婦二人でローンを組む方法もあります。
夫婦で組むローンは、金融機関や商品によって仕組みが異なります。二人の働き方に合わせて選ぶと良いでしょう。
「ペアローン」は、おもに民間銀行で採用されている仕組みです。夫と妻それぞれが金消契約を結び、互いに相手の連帯保証人となって返済を保証し合います。夫と妻で異なる金利タイプや返済期間を設定でき、住宅ローン控除も各々受けられる点がメリットです。共働きで、二人とも一定の収入がある場合に適しています。
「収入合算(連帯債務型)」は、フラット35やろうきんで採用されている仕組みです。ペアローンと異なり契約は一本で、夫婦の一方が主債務者/もう一方が連帯債務者となります。住宅ローン控除は、ペアローンと同様、各々受けることができます。
別の金融機関で再審査
インターネットで「審査に通りやすい銀行」といったキーワードで検索したことのある方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、「誰にとっても」審査に通りやすい銀行はありません。
一方で、金融機関によって重視される審査項目には個性があります。○○銀行では融資が認められなかったけれど、△△銀行では審査に通る――そんな例は珍しくありません。
例えば、団体信用生命保険に健康上の理由で加入できないとします。確かに加入を条件とする銀行は多いですが、フラット35のように団信加入は任意としているローンも存在します。
大切なことは、不動産会社によく相談して、自分の状況にあった金融機関や商品を探すことです。不動産会社と提携している金融機関や、メインバンクとして預金口座をもっている銀行では、優遇金利が適用されるなど、有利な条件で契約できる場合もあります。
個人信用情報が原因の場合は……
公共料金の支払いや、クレジットカードの引き落とし、キャッシングの返済等が遅れると、CIC・JICC・KSCといった信用情報機関にネガティブな記録がつきます。支払いが61日以上遅れると「異動」の記録がつき、どの金融機関でも審査は極めて不利になります。
「うっかり支払いを忘れてしまったら、一生住宅ローンを組めないの?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、安心してください。
異動の記録は、滞納してしまった支払いを完済した日から5年で消える仕組みになっています。5年経過して記録が消えれば、その後は審査に影響することはありません。
まとめ
住宅ローン審査に落ちてしまう理由は、年収や返済比率、年齢、個人信用情報などさまざまです。住宅ローンの利用を検討している方は、普段から支払いの滞納などをしないよう気をつけましょう。
審査に落ちてしまう原因が返済比率にあるのであれば、頭金を増やして借入額を減らしたり、ペアローンや収入合算といった別の方法で対応できる可能性があります。
年齢など属性が問題になった場合、重視される項目や基準は金融機関によって異なりますから、別の金融機関であれば審査に通る可能性もあります。
自分の状況に合わせて最適な金融機関やプランを選び、資金計画を立てることが大切です。
住宅リノベーションのひかリノベでは、物件探しや住宅ローンのご相談からワンストップでマイホーム計画をサポートいたします。審査の不安、適正な予算など、住まいとお金に関する相談も遠慮なくお申し付けください。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。
タを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。