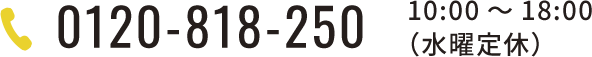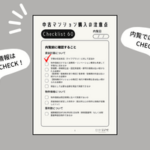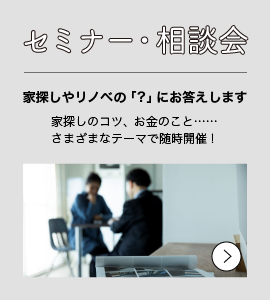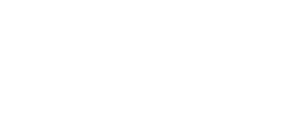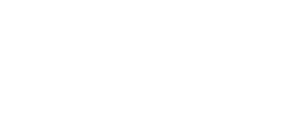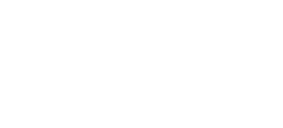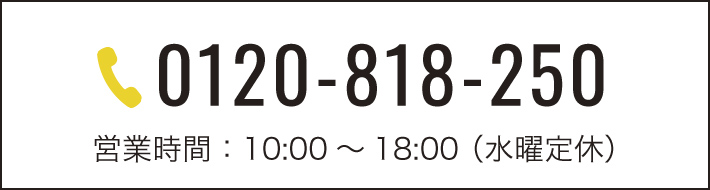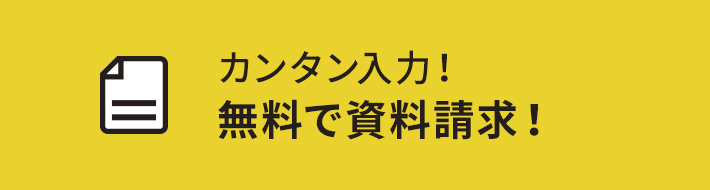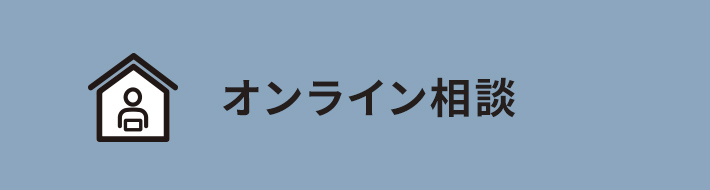中古マンションの購入には、物件代金のほかに手数料や税金がかかります。
「いくらの物件が買えそうか」と予算を考えるときは、こうした各種諸費用も込みで考えなくてはいけません。
また住宅ローンを利用する場合にも、現金で用意しなくてはいけない初期費用があります。
この記事では、中古マンション購入の諸費用は「いつ・何を・いくら支払うのか?」を解説します。
目次
「諸費用」って何? 金額の目安は?
中古マンション購入時に必要な諸費用の目安は、物件価格の5~8%。
引越し費用や入居後に納める税金を含めると、およそ10%と考えておけば良いでしょう。
新築マンションや新築戸建てでは、物件価格の3〜6%が目安とされています。中古の方が割合が大きいのは、不動産会社の仲介手数料がかかるためです。新築は基本的に直販ですが、中古は売主も買主も個人同士のため、その間を仲介する不動産会社が必要となります。
ただし、中古であっても不動産会社が買取再販している物件もあります(リフォーム済み物件などに多いです)。販売元から直接購入した場合には、仲介手数料は掛かりません。
諸費用は、従来は現金で用意するものとされてきました。現在は諸費用も含めて全額住宅ローンで借りることも可能となりましたが、実際には従来どおり諸費用相当額を頭金として現金で支払う人が多数派です。
どんな費用がかかるの? 諸費用の中身と概要
諸費用とは、購入に際してかかるさまざまな「手数料」や「税金」などの総称です。
中古マンションの購入には、不動産会社や銀行・保険会社・司法書士など、さまざまな事業者が関わります。サービスの対価や、面倒な手続きの代行料金、諸経費を支払わなくてはいけません。
また、不動産(資産)を取得すると「固定資産税」や「不動産取得税」といった税金が課せられます。登記費用もかかります。
手数料・サービス料
| 費用 | 概要 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う、物件のマッチングや契約・決済・引き渡し手続きのサポートに対する手数料。金額は物件価格の3%+6万円(消費税別) |
| 融資事務手数料 | 金融機関に支払う、住宅ローンを組むための手数料。金額は金融機関によって異なる。 |
| 保証料 | 住宅ローンが途中で返済不能となった場合、保証会社が代わりに弁済する。そのための保証料。金額は金融機関や融資金額によって異なり、一括支払いのほか、住宅ローンの金利に組み込める金融機関もある。 |
| 団体信用生命保険料 | 住宅ローンを組むために、多くの金融機関では団体信用生命保険(団信)への加入を義務付けている。その保険料。通常は住宅ローンの金利に含まれており、別途支払いの必要はないが、一部の金融機関で例外もある。 |
| 火災保険料 | 住宅ローンを組むために、多くの金融機関では火災保険への加入を義務付けている。その保険料。金額は保険会社や保障内容によって異なる。 |
| 登記手数料 | 司法書士に支払う、物件の所有権移転や、ローンの抵当権設定の登記手続きの代行報酬。金額は司法書士によって異なる。 |
| 管理費・修繕積立金 | マンション管理組合に納める、マンションの管理運営や、建物の修繕のための費用。購入後は毎月納める。金額はマンションによって異なる。 |
税金
| 費用 | 概要 |
| 印紙税 | 契約手続きに際して納める税金。売買契約、ローン契約にそれぞれ課税される。印紙を貼って納める。税額は契約金額に応じて決まる。 |
| 登録免許税 | 登記登録に際して納める税金。所有権移転登記、抵当権設定登記に課税される。税額は、所有権移転登記は土地や建物の評価額に、抵当権設定登記は融資金額に応じて決まる。 |
| 固定資産税 | 不動産の所有者に課せられる税金。購入後は毎年納める。税額は土地や建物の「固定資産税評価額」に応じて決まる。 |
| 都市計画税 | 都市計画区域内に不動産を所有する人に課せられる税金。購入後は毎年納める。税額は土地や建物の評価額に応じて決まる。 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した人に課せられる税金。購入後に一度だけ納める。 |
いつ・いくら支払う?支払いの時期と金額
中古マンション取引においては、売買契約から決済・引き渡し時までの間に、およそ1ヶ月のタイムラグを空けるのが一般的です。
この間に、売主は退去して部屋を空け、買主は住宅ローンの審査を受けて融資の実行を待ちます。
金銭の授受が生じるのは基本的に決済のタイミングですが、売買契約のタイミングで支払う費用も一部存在します。手付金や売買契約の印紙税、不動産会社によっては仲介手数料の一部をここで支払います。
『手付金』とは、「物件代金の一部を売主に預け、もし契約をキャンセルする場合にはこれを放棄する」というもの。物件価格の全額をローンで借りる場合、融資実行のタイミングでこのお金は戻ってきますが、契約時には一旦現金で用意しなくてはいけません。
『売買契約の印紙税』も同様で、たとえ諸費用を全額ローンで借りる場合であっても、この時点ではまだ融資が実行されていないので、現金で用意する必要があります。
ほとんどの諸費用、すなわち仲介手数料(一部を先払いした場合は、その残り)、各種保険料や税金、管理費・修繕積立金は、決済のタイミングで物件代金と一緒にまとめて支払います。ここまでが初期費用です。
このあと購入から半年後〜1年後に発生するのが『不動産取得税』。
『管理費・修繕積立金』は購入したときから毎月、『固定資産税・都市計画税』は毎年支払い続けることになります。
この他、リフォームやリノベーションをおこなう場合は、工事の着工時・完工時(場合によっては中間金も)と2〜3回に分けて工事費の支払いが発生します。
| 支払い時期 | 発生する費用 |
| 売買契約時 |
|
| 決済時 |
|
| 引き渡し後 |
|
| 購入後継続して支払う |
|
諸費用の内訳、とくに税金の計算はなかなか分かりづらいものです。総額はおおよそ物件価格の10%と考えておけばOKですが、詳しい内訳金額が知りたい方は、担当のコーディネーターに問い合わせてみてください。
3,000万円の中古マンションを購入した場合の諸費用をシミュレーション
具体的にそれぞれの手数料や税金にいくらかかるのか、以下の物件をフルローンで購入したと仮定して、大まかな金額を計算してみましょう。
物件価格3,000万円の中古マンション
- 土地評価額1,000万円
- 建物評価額2,000万円
- 土地の持分80㎡
この物件にかかる諸費用(手数料・税金)をすべて合計すると、
- 仲介手数料…………………105万6,000円
- 融資事務手数料……………3万3,000円
- 保証料………………………60万円
- 団体信用生命保険料………0円
- 火災保険料…………………15万円
- 登記手数料…………………10万円
- 管理費・修繕積立金………3万円
- 印紙税………………………3万円
- 登録免許税…………………24万円
- 固定資産税…………………30万3,000円
- 都市計画税…………………7万円
- 不動産取得税………………0円
(合計)およそ261万円。
物件価格の87%となりました。
それでは、各費用の具体的な計算方法を見ていきましょう。
仲介手数料
仲介手数料の法定金額は「物件価格の3%+6万円(税抜)」。
物件価格3,000万円とすると税抜96万円。消費税込で105万6,000円となります。
融資事務手数料
金融機関ごとに金額設定が異なりますが、メガバンク系は「3万円(税抜)」としている銀行が多いようです。
この場合、消費税込で3万3,000円となります。
保証料
金融機関ごとに金額設定が異なりますが、メガバンク系は一括支払いの場合、35年ローンで100万円あたり約2万円(税込)。
利息組込み型の場合、金利が0.2%上乗せとしている銀行が多いようです。
中にはフラット35のように、保証料がない(金利にあらかじめ含まれている)商品もあります。
ここでは民間金融機関でローンを組み、一括支払いを選択したと仮定しましょう。
3,000万円の借入なので、およそ60万円となります。
団体信用生命保険料
団信の保険料は、多くの金融機関が予め利息の中に組み込んでおり、別途支払いは不要です。
火災保険料
保険会社によって金額設定が異なりますが、一般的な保障内容(火災・落雷・風災の10年補償、地震の5年補償)で、15万円程度というケースが多いです。
登記手数料
司法書士によって金額設定が異なりますが、地域ごとの相場があります。
都内の場合、所有権移転登記と抵当権設定登記で10万円〜が目安です。
管理費・修繕積立金
マンションによって金額設定が異なりますが、平均的な金額は合わせて毎月2〜3万円です。
とくに修繕積立金は、築年数が古いほど高くなる傾向があります。
ここでは仮に3万円としましょう。
印紙税
売買契約書等の契約書に印紙を貼り、その印紙代という形で納税します。
売買契約、ローンの契約にそれぞれ課税されます。
(リフォームやリノベーションをする場合は、その工事請負契約にも)
課税額は、印紙税法に基づき、契約の内容と金額に応じて決まります。
売買契約と工事請負契約には、下記の表の右側の軽減税率が適用されます。
ローンの契約には、左の本則税率が適用されます。
3,000万円のマンション購入であれば、売買契約の印紙税は1万円、ローン契約の印紙税は2万円となります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 100万円~500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万~1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万~5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万~1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億~5億円 | 100,000円 | 60,000円 |
参照:国税庁 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0018003-093-01.pdf
登録免許税
所有権移転登記については土地や建物の評価額に、抵当権設定登記については融資金額に応じて税額が決まります。
所有権移転登記の登録免許税額は、土地と建物で税率が異なり、土地は評価額の1.5%、建物は評価額の0.3%です。
本例の場合、土地に課される税額は1,000万円の1.5%で15万円。建物は2,000万円の0.3%で6万円です。
抵当権設定登記の課税額は、融資金額の0.1%ですから、3,000万円の0.1%で3万円です。
| 登記の種類 | 税率 |
| 所有権の移転登記(土地) | 1.5% |
| 所有権の移転登記(建物) | 0.3% |
| 抵当権の設定登記 | 0.1% |
参照:国税庁 登録免許税の税額表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
固定資産税
土地や建物の評価額に応じて税額が決まります。
土地の税率は1.4%、ただし土地の持分に応じて、税額を控除する軽減措置が適用されます。
本例では土地の持分は80㎡なので、1,000万円の1.4%に1/6を掛けて、約2.3万円となります。
建物の税率は1.4%なので、2,000万円の1.4%で、28万円となります。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して、毎年4月に1年分の納税通知書が送付されます。
そのため購入した年の納税は、引き渡し日を基準に日割りで折半するのが一般的です。2年目以降は、全額を毎年納税していきます。
| 課税対象 | 標準税率 | 軽減措置 |
| 土地 | 1.4% | (200㎡までの部分)1/6 |
| (200㎡を超える部分)1/3 | ||
| 建物 | 1.4% | – |
参照:東京都主税局 固定資産税・都市計画税の概要 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html
都市計画税
土地や建物の評価額に応じて税額が決まります。
土地の税率は1.4%、ただし土地の持分に応じて、税額を控除する軽減措置が適用されます。
本例では土地の持分は80㎡なので、1,000万円の0.3%に1/3を掛けて、1万円となります。
建物の税率は0.3%なので、2,000万円の0.3%で、6万円となります。
都市計画税は、固定資産税とセットで納税通知書が送られてきます。そのため購入した年の納税は、こちらも同様に日割りで折半するのが一般的です。
| 課税対象 | 標準税率 | 軽減措置 |
| 土地 | 0.3% | (200㎡までの部分)1/3 |
| (200㎡を超える部分)2/3 | ||
| 建物 | 0.3% | – |
参照:東京都主税局 固定資産税・都市計画税の概要 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html
不動産取得税
土地や建物の評価額に応じて税額が決まります。
土地・建物ともに税率は3%ですが、一定のおを満たす中古住宅については特例があります。
土地は評価額を半額として計算し、さらに一定の金額(表を参照)を控除します。
建物については、築年数に応じて最大1,200万円が控除されます。
一定の要件とは、専有部分の床面積が50〜240㎡であること、新耐震基準に適合していることの二つです。
本例ではどちらも満たすと仮定すると、土地・建物とも0円となります。
| 課税対象 | 本則税率 | 控除額 |
| 土地 | 3% | 評価額を半額とし、 ①45,000円 ②1㎡の評価額の1/2 × 占有面積の2倍(最大200㎡) × 3% ⇒①②いずれか多い方を控除する |
| 建物 | 3% | (平成9年4月1日以後築)1,200万円 |
| (平成元年4月1日~平成9年3月31日築)1,000万円 | ||
| (昭和60年7月1日~平成元年3月31日築) 450万円 | ||
| (昭和56年7月1日~昭和60年6月30日築) 420万円 | ||
| (昭和51年1月1日~昭和56年6月30日築) 350万円 | ||
| (昭和48年1月1日~昭和50年12月31日築)230万円 | ||
| (昭和39年1月1日~昭和47年12月31日築)150万円 | ||
| (昭和29年7月1日~昭和38年12月31日築)100万円 |
参照:東京都主税局 不動産取得税の概要 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
諸費用も住宅ローンで借入できる?
諸費用は、従来は現金で用意するものとされてきましたが、現在は諸費用まで全額住宅ローンで借りることも可能になりました。しかし実際には、諸費用相当額を頭金として現金で用意する方が多数派です。
住宅ローンはいくらでも借りられるわけではありません。ローンを組むには審査があり、年収や年齢、健康状態などのさまざまな基準を満たしている必要があります。さらに借入額や返済期間についても、「無理なく返せる」と判断された範囲内でしか認められないのです。
従来は融資金額の上限を「物件価格の80%」としている銀行が多かったため、頭金として物件価格の2割程度の現金を用意する必要がありました。しかし現在では、「返済が十分可能でさえあれば、物件価格の全額や諸費用までも融資を認める」という銀行も増え、頭金なし(現金の用意なし)でローンが組めるケースも多く出てきました。
とはいえ、借入金額が大きくなればそれだけ返済が大変になります。さらに、ローンには利息もかかります。最終的に支払わねばならない金額を考慮して「諸費用は現金で用意する」という住宅購入者が大半です。
諸費用を抑える方法は?
諸費用は前述の通り、現金で用意するのが一般的です。しかし現金で用意するのが難しいという人もいるでしょう。そのような場合に諸費用の金額をおさえる方法はあるのでしょうか。
保証料がかからない住宅ローンを選ぶ
住宅ローンの保証料の金額や支払い方法は、金融機関によって異なります。
前出の通り、メガバンク系の住宅ローンでは、保証料が35年ローンで100万円あたり2万円となっています。一括払いの場合は、数十万円規模の大きな出費になるでしょう。
一方で、たとえば住宅金融支援機構の「フラット35」であれば、金利にあらかじめ含まれているため保証料がかかりません。ただし、フラット35を利用するには技術基準があり、新耐震基準のマンションであることなどの制約があります。基準に合致する物件であれば、保証料の節約のためフラット35などの利用も選択肢の一つとなるでしょう。
火災保険の補償内容を絞る
火災保険の補償内容を絞るのも、諸費用を抑えるのに有効です。火災保険の補償内容に無駄がないか、見直してみましょう。
火災保険の一般的な保障内容には、火災による損害はもちろん、盗難や配管の水漏れ事故、台風被害や水災、雪災のほか自賠責保険などが含まれています。高台エリアにある物件やマンションの高層階など、水災による床上浸水の被害が想定されにくい場合にはその項目を外すなどすると保険料を下げられます。
金融機関によっては保険会社と提携していて、そこの火災保険に入ると保険料の割引や住宅ローンの金利優遇を受けられる場合も。ただしこの場合、補償内容があらかじめ固定されていて、自由に選べないこともあるので要注意。
いずれにせよ、火災保険を決める場合には、補償内容とかかる金額をよく考えて決断することがポイントです。
まとめ
今回ご紹介した、手数料や諸費用の計算はなかなか理解しづらいもの。細かな計算なども必要になるため、住宅購入を検討している方は事前に不動産会社や中古物件も扱っているリノベーション会社の担当者に確認してみると良いでしょう。
当社ひかリノベでは、物件探しからリノベーション、資金計画までワンストップでお住まいづくりをサポートいたします。住まいとお金に関する不安や疑問も、コーディネーターがご相談を承りますので、安心してご相談ください。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。