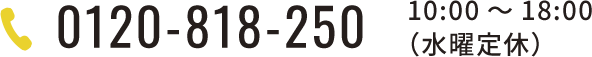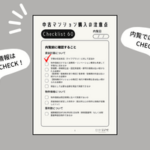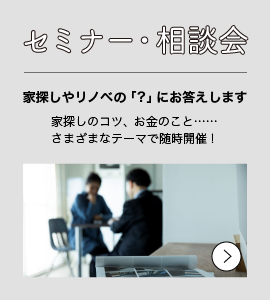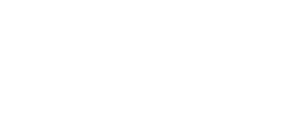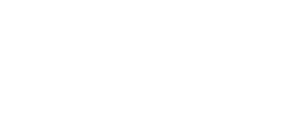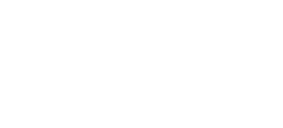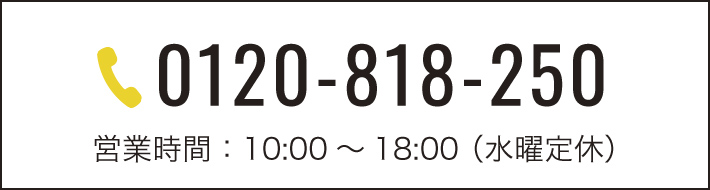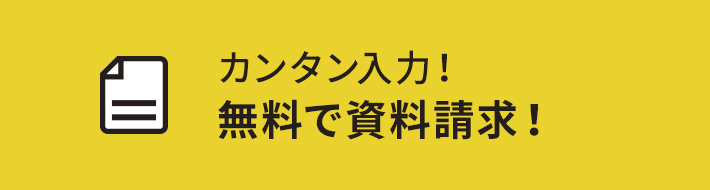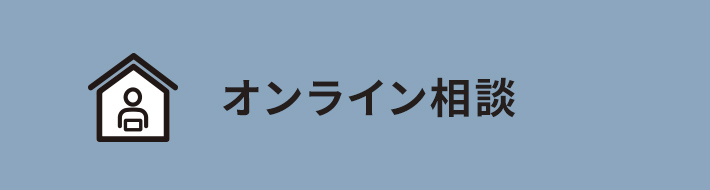「自宅で楽曲制作をしたい」「録音した音を編集したい」という場合に便利なのが、レコーディングスタジオです。最近ではYouTubeやSNS等で、自分の作成した音源を流したいという人も増え、ますますレコーディングスタジオの必要性が高まっています。
そこでこちらの記事では自宅にレコーディングスタジオを造る際の注意点や費用相場などを詳しく解説。実際に施工した事例を参考に、自分なりのレコーディングスタジオを考えてみましょう。
目次
レコーディングスタジオを造る前に
レコーディングスタジオを造る前に重要なのが、どのような目的で使用したいかということ。
レコーディングスタジオは、ブースとコントロール・ルームに分けられます。それぞれの役割はこちらです。
| 名称 | 役割 |
| ブース(スタジオ) | 楽器を演奏したりボーカルの歌声を収録する場所 |
| コントロール・ルーム | 録音機材を使用した録音や、録音した音源を編集・ミキシング・マスタリングする場所 |
ブースは使用する楽器によって広さや防音性能を変える必要があります。またコントロール・ルームもどのような機材を使用するかによって、部屋の広さを決めなければなりません。もちろん楽器の編成や録音スタイルによっても、レコーディングスタジオの構成が変わってきます。
ブースの広さや使用する楽器に適した防音性能、騒音レベルによって、レコーディングスタジオの施工費用が大きく変わってくるため、どのような目的でスタジオを使用したいかという意図を明確にする必要があるのです。
レコーディングスタジオ工事の注意点
実際に自宅にレコーディングスタジオを造る場合は、次のようなポイントに注意しましょう。
室内から室外への音漏れ
レコーディングスタジオのブースは、第一に室内から室外への音漏れがないように注意する必要があります。
演奏する楽器の種類によって、音の大きさや音の伝わり方は異なり、必要な防音工事も変わってきます。
楽器や音量に応じた遮音性能がないと、演奏する音が外にもれて苦情の原因に。
こちらは音源ごとの音の強さを示すデシベル(dB)です。
| 楽器 | 音の強さ(dB) |
| ピアノ | 90~100デシベル |
| ボーカル | 100~110デシベル |
| ドラム | 110~120デシベル |
防音室設計の考え方として、防音工事だけで「120dBの音を防がなくてはならない」というわけではありません。建物本来の防音性能もあるためです。
ただし、建物本来の防音性能は、建物構造(木造・S造・RC造など)によっても異なります。
また管楽器やドラムなどの打楽器は、小さな音量で演奏することが難しく、他の楽器以上に高い遮音性能が求められます。
本来の住宅環境と使用目的に合わせて、目標とする遮音レベルを予め決めておくことが重要です。
壁や床だけでなく、空調のダクトや電気設備等の配線処理にも注意が必要です。これらの設備は遮音構造を貫通するため、その隙間から音が外にもれだす可能性が。
このような部分の処理にも同じ遮音レベルの部材を使用するようにしましょう。
室外から室内への音の侵入
いい音を録音するためには、外の音を室内に入れない対策も必要です。幹線道路沿いの住宅や近くに繁華街がある住宅地では、音漏れの心配よりは外からの音の侵入の方が気になるという場合があるでしょう。
外からの音の侵入を減らすためには、壁の補強や、ドアを隙間の無い防音ドアに変更するといった対策のほか、窓サッシを防音用サッシに替えるという方法も有効。
いずれの場合も部屋のどの部分から外の音が入ってくるかという「音の進入口」をしっかり確認して、外から入ってくる騒音の音量を減らすことが重要になります。
床や壁を伝わる振動の対策
楽器の演奏は「音」だけでなく、床や壁を伝わる「振動」にも対策も必要です。録音ができる静かなブースを造るためには、音だけでなく振動も遮断しなければなりません。
上階で扉を開け閉めしたり、大きな足音で歩いたりすると、下の階に衝撃音と共に振動が伝わるのを経験したことがある人も多いでしょう。
ピアノやドラムなど、床に直接置いてペダルを踏み込んで演奏する楽器を使用する場合、その振動が床から建物の躯体を通して、他の部屋や階に伝わってしまう可能性があります。
吸収面による音の響きの調整
レコーディングスタジオを造る場合は、ブース内で音を響かせすぎず、適切な響きの長さ(残響時間)に調整する必要があります。
音が響きすぎると元の音が分からなくなり、レコーディングのクオリティにも悪影響です。
逆に音の残響時間が短すぎると、本来の音色が出ない楽器もあるため、使用する楽器や目的に応じた吸音率を設定するようにしましょう。
吸音率は音の残響時間が長い「ライブ」から、残響時間が短い「デッド」まで数値で示します。こちらは使用する楽器や目的ごとの推奨吸音率の一覧です。
| 推奨吸音率 | 使用目的 |
| ライブ | 弦楽器 |
| 0.15 | 声楽 |
| 0.19 | ピアノ |
| 0.24 | フルート・クラリネット |
| 0.30 | トランペット・トロンボーン |
| 0.40 | オーディオルーム・シアタールーム |
| デッド | ドラム |
吸音率はレコーディングスタジオの設計段階で設定します。
防音室の設計に関する注意点やポイントは、こちらに特集記事がありますので、詳しく知りたい方は下記の記事も併せてご覧ください。
レコーディングスタジオ工事の費用の目安
RC造マンションにレコーディングスタジオを造る場合、既存面積ごとの費用の目安はこちらです。
| 既存面積(畳) | 既存面積(㎡) | 価格(円) |
| 3 | 5.0 | 280万 |
| 4 | 6.6 | 330万 |
| 5 | 8.3 | 360万 |
| 6 | 9.9 | 390万 |
| 7 | 11.6 | 420万 |
| 8 | 13.2 | 440万 |
※専有区画外/躯体スラブを合わせた複合遮音性能D-65~70(開口部を除く)
※建具・サッシのサイズおよび仕様により金額の変動があります。
※電子ドラムを想定(生ドラムは使用不可)
ブース内を確認できるようブースの壁にガラスをはめ込んだり、コントロール・ルームへのドアにガラス入りのものを使用したりすると、施工費用は変動します。
レコーディングスタジオの施工事例
こちらでは実際に自宅にレコーディングスタジオを施工した事例をもとに、取り入れたいポイントやこだわりの箇所を紹介していきます。
戸建住宅の地下に施工したレコーディングスタジオ

こちらは戸建ての地下に施工した、本格的なレコーディングスタジオの事例です。
レコーディングスタジオ全体が統一されたデザインで、細部までこだわったかっこいいスタジオに仕上がっています。

ブースの隣にあるコントロール・ルームには、モニターコントローラーを設置して、ブーストのコミュニケーションも快適。
所々に間接照明を配置して、クライアント様も納得の大人っぽい空間が完成しました。
閑静な住宅街の一軒家にレコーディングスタジオを施工

こちらはブースとコントロール・ルームを逆L字に配置したレコーディングスタジオです。
床全体をヘリンボーン柄のフローリングで仕上げ、モノトーンのレンガを使用するなど、内装にもこだわりが感じられます。

コントロール・ルームからブース内をチェックするために、大き目の防音サッシを設置。中の様子を確認しながら、遮音性もキープしています。
まとめ
自宅のレコーディングスタジオは音楽をする人にとって、気軽に音楽を配信したり、本格的なレコーディングができるなどのメリットがあります。
しかし良い音を作って録音するには、室内の音を外に漏らさず、外の騒音を室内に入れない対策が必要。また床を伝わる振動問題対策や、残響時間を計算した吸音設計も欠かせません。
しっかりとした生音を出せる環境にするには、防音工事の専門家に工事を依頼するのが一番。
この度ひかリノベは、防音工事の専門家である昭和音響さんと業務提携しました。
昭和音響さんは防音工事のスペシャリストとして、一般住宅のみならず店舗やライブハウスの防音工事も手掛けています。
マンションのフルスケルトンリノベーションを行っているひかリノベと、防音工事の専門家・昭和音響さんがタッグを組んだことで、さらにマンションリノベのバリエーションが広がります。
ご自宅をリフォームするタイミングでレコーディングスタジオや音楽スタジオを新設したいとお考えの方は、ぜひひかリノベにご相談ください。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。