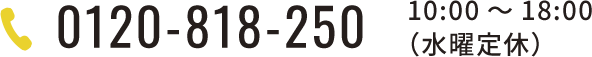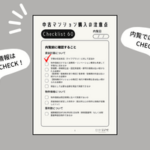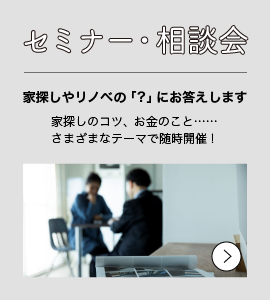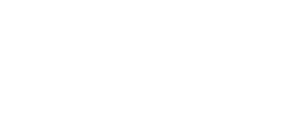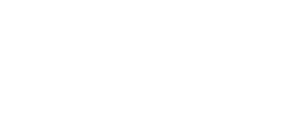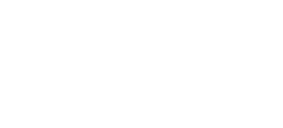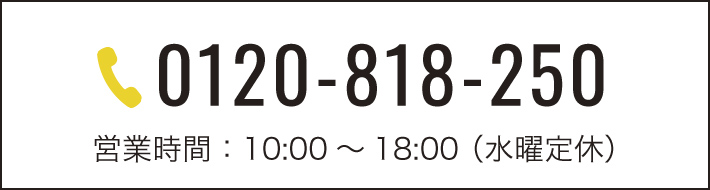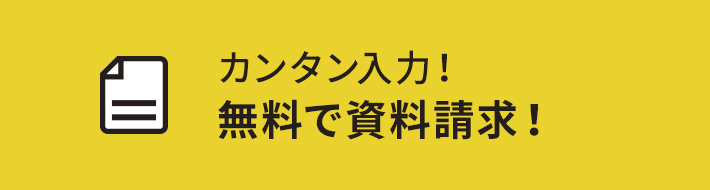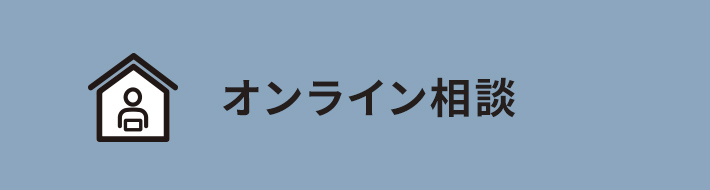マンションでは隣人の話し声や子どもの足音、ペットの鳴き声などがトラブルの原因となることがあります。また屋外の喧騒や、自動車の走行音といった騒音が問題となることも。
静かで快適な暮らしをしたいなら、防音性能に注意して物件を選ぶ必要があります。しかし、防音性能の高いマンションを見つけるのは簡単ではありません。
この記事では、物件選びで注意すべき防音性能の見分け方、そしてリフォームで防音工事を行う際のポイントや注意点について解説します。
目次
防音性能の高いマンションの特徴とは?
まずは防音性能の高い建物の特徴について解説します。
建物の防音性能を左右するポイントとして、建物構造、壁、床、窓サッシがあります。
物件情報を見るときは、これらを意識してみると良いでしょう。
建物構造
音を通しにくい建物構造は、第一に鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)。
次に鉄骨造(S造)。
最後に木造という順番になります。
躯体に使用している建材の重量が重ければ重いほど、音を通しにくくなります。RC造は、床も壁も重いコンクリートで出来ています。壁は乾式遮音壁という場合もありますが、これも遮音性の高い素材です。
ただし、床や壁にどの素材を採用しているかだけでは、一概に遮音性能は判断できません。間取りや周辺環境、窓サッシなど、音漏れの原因は複数あります。
したがって「RC造だから安心だろう」ではなく、内見の際に実際の聞こえをチェックすることが大切です。
壁の厚み
人の話し声やTV・オーディオの音声といった空気伝搬音を防ぐには、壁の厚みがポイントになります。
成人が発する声のボリュームは、おおよそ約55dB(デシベル)。
コンクリート壁の場合150~180mm以上の厚みがあれば、通常は生活音に紛れて気にならない音量になります。
乾式遮音壁の場合、遮音等級D-55以上(特級クラス)を採用している物件が安心でしょう。
ただし、壁の遮音性がいくら高くても、床や天井などの取り合いに隙間があれば、そこから音漏れする可能性があります。たとえば、隣戸と接する壁(戸境壁)にコンセントやスイッチがあると、そこから音が漏れてくる可能性もあります。
床の厚みと仕上げ
人の歩く足音や、モノを落としたとき、上階から下階に響く音を防ぐには、床がポイントになります。
人の足音のような「ドスン」という重量衝撃音は、躯体のコンクリートの厚みが重要です。大人が静かに歩く足音は180mm以上、子供が走り回る足音は200mm以上の厚みがあればほぼ気にならなくなります。
ナイフやフォークを落としたときの「カツン」という軽量衝撃音は、床材によって軽減が可能です。最近のマンションは、遮音フローリングを採用している物件が増えていますね。この遮音フローリングの中でも等級があり、日本複合・防音床材工業会では、LL-45以下のものを推奨しています。
また、床の仕上げ方でも、音の伝わりやすさが変わってきます。二重床工法を採用しており、躯体と仕上げの床の間に100mm程度の空気層を設けているとか、緩衝材を詰めているといった物件は、直床工法の物件に比べて音が響きにくいです。
窓サッシ
通行人の話し声、車や電車の走行音など、屋外から窓をつうじて入ってくる音もあります。これらの外部騒音を防ぐには、窓サッシの性能がポイントになってきます。
街の喧噪を防ぎたいという場合は、遮音等級T-1以上、道路や線路沿いの物件で、車や電車の走行音を防ぎたい場合は、T-2以上のグレードの窓サッシがおすすめです。
窓ガラス自体に厚みがあったり、緩衝材入りの複層ガラスなど、防音仕様のガラスもありますが、サッシの気密性が低ければ、隙間から音が入り込み、あまり意味がありません。
また、二重窓(二重サッシ)もおすすめです。外窓と内窓のあいだの空気層が音の緩衝材となり、遮音性が向上します。
音が気になりにくい間取りは?
居室同士が隣り合わないよう設計されている物件は、隣戸の話し声や生活音が気になりにくいです。
たとえば隣接する部屋同士の間に、互い違いにクローゼットや押入れなどの収納が配されていると、洋服や布団など中に収納しているモノが音を吸収し、居室までは音が届きにくくなります。
あるいは、キッチンや浴室などの水廻り同士が隣り合う間取りも、音が気になりにくいです。トイレやバスルームは使うとき以外は立ち入ることがないため、音の緩衝地帯になります。
また、PS(パイプスペース)の位置にも注目してみましょう。PSは給水配管・排水配管の本管であり、水を使うと流水音がします。流水音は静まった居室に響きますので、PSが居室に接しない間取りがベターと言えます。
立地や周辺環境も騒音に繋がる?
大型車両が通る幹線道路や線路沿いのマンションは、いくら壁を厚くしたり、防音サッシを設置したりしても無音という訳にはいきません。騒音が気になるようなら、幹線道路や線路が目の前にあるマンションは避けた方が賢明でしょう。
また、車や電車の音は気にならなくても、通行人の声や、近隣のコンビニ・スーパーの音が多い環境がストレスになる場合もあります。自分はどのような種類の音を不快に感じるかをよく考え、近隣に不快に感じる音の発生源がないか確認しながら、住まい探しを進めましょう。
一方で、繁華街に近い物件は外の喧騒が気になりやすいゆえに、前述のような壁の厚みや窓サッシなどが防音仕様となっている場合も多く、室内は意外なほど静かな物件も珍しくありません。やはり内見の際に、実際の音の聞こえ方を自分の感覚で確認してみることが大切です。
目的別・物件選びのポイント
どんな音を防ぎたいかによっても、物件選びのポイントは変わってきます。目的別に、とくに注意したいポイントを紹介します。
生活音が聞こえにくい部屋とは?
周囲の生活音を少しでも気にせずに生活したい場合は、接する住戸が少ない住居を選ぶとよいでしょう。周囲の騒音リスクを避けやすくなります。
最上階の角部屋なら、上階から発生する足音に悩まされることもなく、接する隣戸は一方のみなので、話し声が聞こえるリスクも半減します。
子供の足音が近所迷惑にならない部屋は?
小さな子供がいると、足音や飛び跳ねる音が周囲の迷惑にならないか心配、という方も多いですね。その場合、一階の住戸がおすすめです。子供が走り回ったり飛び跳ねたりしても、階下に足音が響く心配がありません。
また、どんな世帯が多い物件なのか、不動産仲介会社を通じて聞いておくとより安心です。同じような年頃の子供をもつファミリー世帯の入居者が多いマンションのほうが、子供が発する騒音について、理解が得られやすい傾向があります。
楽器演奏ができる部屋の探し方は?
マンションでの楽器演奏は、通常は管理規約によって禁止されている場合が多いです。まずはマンションの管理規約を確認し、楽器演奏が認められている物件を探しましょう。
音大などがあるエリアでは、楽器演奏を想定した防音対策がなされ、「楽器演奏可」をアピールポイントとしている物件が見つかりやすいようです。
あるいは、リノベーションで防音室をつくる方法もあります。この場合、ピアノ、ドラム、管楽器など、演奏する楽器に合わせ、最適な防音室を自由設計でつくることが可能です。
防音室リフォームの費用や工事方法については、下記の特集記事があります。よろしければこちらも併せてご覧になってみてください。
リフォームで防音性能を高める
ここまで物件選びの際に注意したいポイントについて述べてきましたが、リフォームやリノベーションによって防音性能を高める方法もあります。
たとえば、壁や床の遮音性能は、「床下地・壁下地を組んで緩衝材を詰める」「床材を遮音フローリングに変える」などの方法で、躯体には触らずに性能向上ができます。
窓サッシはマンションの場合共用部分となるため勝手に交換することはできませんが、既存のサッシには触らずに内窓(二重窓)を設置する方法であれば、リノベーションの範疇で可能です。
また、カバー工法といって、既存のサッシの上に樹脂アルミ複合サッシを被せ、気密性を高める方法もあります。こちらは管理組合の許可が必要ですが、申し出れば認められる場合が多いです。
間取りの変更や家具のレイアウトによって音を低減することもできます。たとえば戸堺壁側にクローゼットを配置する、本棚や洋服箪笥を置くなどの方法があります。
テレビやオーディオは、戸境壁側に置くのがおすすめ。音は前に向かって出るので、自分の置いたテレビの音が隣の迷惑になるリスクも避けられます。
まとめ
マンションの防音性能を左右する要素をいろいろお伝えしてきましたが、音の問題はさまざまな要素が絡んでくるので、物件選びの際はなによりも「実際の音の聞こえをチェックすること」が大切です。内覧の際は、ぜひ目で見るだけでなく耳も澄ませて、音の聞こえ方をよく確認してください。
当社ひかリノベは、物件探しからリノベーションまでワンストップで提供するリノベーション会社です。
家探しからのリノベーションをご希望の方は、物件探しから設計・施工まで。
居住中のご自宅のリノベーションは、工事中の仮住まい探しから設計・施工まで、ワンストップでおまかせいただけます。
楽器演奏を想定した防音室の設計施工も、豊富な実績がございます。楽器演奏が可能なマンションが見つからないとお困りの方は多いです。ぜひ当社ひかリノベまでお気軽にご相談ください。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。