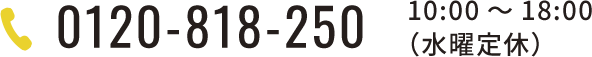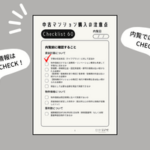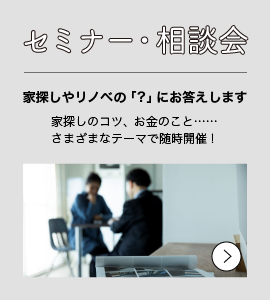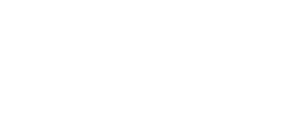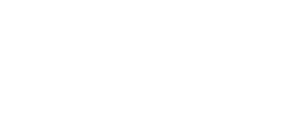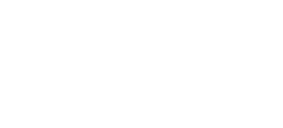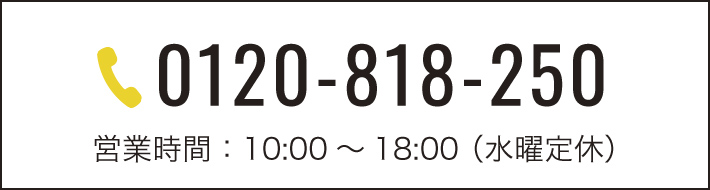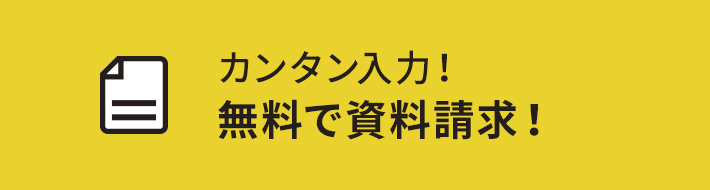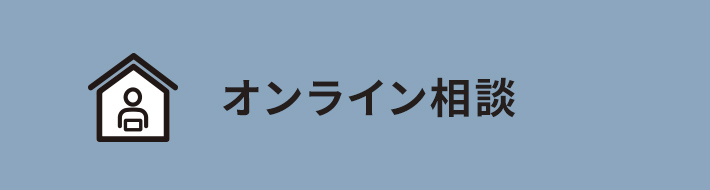リノベーションをして、出来上がった理想のマイホーム。でも「なんだかイメージが違う…!?」そのように感じる原因は、家具にあるかもしれません。
内装はいわばキャンバス。家具選びが理想の部屋をつくる最後のピースです。
リノベーションをすれば、部屋のテイストはガラリと変わりますが、それに合った家具を選ばなければ、まとまり感のない印象を与えてしまうことも。
家具を選ぶポイントは様々ありますが、今回は「リノベーションから考えた家具の選び方」についてご紹介します。これからリノベーションをする方、リノベーションを終えて家具をお探し中の方も、ぜひご覧ください!
2016年04月29日初出→2020年1月30日更新
目次
家具を買う前に確認したい2つのこと
物件の内装も完成し、いざ家具を配置する際に失敗しないためのポイントを抑えておきましょう。
住まいのサイズと構造の確認
まず、それぞれの部屋の各辺の長さや高さを測り、扉の位置はどこか、コンセントの位置はどこかなど、部屋の基本構造をチェックしておきます。
そこから、「自分にはどんな家具が必要か?」「どんな家具をどこに置くか?」と検討していくわけです。
いくら家具のデザインが良くても、収納力が足りない・使い心地が悪い・置こうと思った場所に収まらなかった……などがあると、理想のイメージとはかけ離れた部屋、デザイン以前に暮らしにくい部屋になってしまいます。
どこにどんな家具が必要か
どの部屋に、どんな家具が必要なのかを考えておくこともポイントです。
例えば、リビングであれば「家族で寛ぐためのソファーやゆっくり読書ができるイス」。
寝室であれば「ベッドや洋服を収納する家具」など、部屋の用途に合わせて必要な家具をピックアップしておきましょう。
さらに、「リビングは友達を呼ぶことが多いから、大きめのソファーがいい!」など、細かい要望も決めておくと、家具選びがスムーズに行えます。
家具配置のコツは、「どのように暮らしたいか」をイメージすることです。
絵を描くように部屋のイメージを思い描くというよりは、家具の用途や目的、使いやすさをまず考えて、どこに何を置くかを決めていきましょう。
空間デザインの考え方
お洒落な部屋を実現するためには、部屋のテイスト、または家具のテイストから創っていく2通りの方法があります。
部屋のテイストから考える方法
まずは、「部屋のテイストから考えていく」という基本的な方法です。
モダン・ナチュラル・アジアンなど、リノベーション会社の事例やカタログから、自分の好みのテイストを最初に決めます。
それらが決まったあとに、テイストに合わせた家具を選び、統一感を出していきます。
家具を主役に考える方法
もう1つは、「家具から部屋のテイストを考えていく」という方法です。
こちらは、すでに自分の決めている(購入している)家具があって、そこから空間を創っていきます。
お気に入りのソファや、ちょっと奮発して買ったテーブルセット。でも、自分の部屋に置いたらなんだか素敵に見えない。「好きな家具が似合う部屋にしたい」……そんなきっかけでリノベーションを考える方も少なくありません。
この場合は家具を主役に、家具のテイストや色に合わせて、あるいは家具が映えるように、内装素材や色を決めていくことになります。
部屋に調和をもたらす家具の選び方
家具の選び方は、選ぶ人の感性や好みによるところが大きいですが、難しいのは、バランスの取り方、部屋全体の調和です。ここでは、部屋にまとまりが出るような家具の選び方を、色とスタイル、2つの面からご紹介します。
カラーコーディネートのポイント
同系色で家具や小物をまとめると、部屋に統一感が出ます。
同系色とは「似通った色」ということですが、下の写真をご覧いただけると分かると思います。

事例:https://hikarinobe.com/constructioncase/case_0068/より。白~グレーで統一した、シンプルなワントーンコーデのリビング。
しかし、全部を同じ色で統一してしまうと、単調になってつまらない印象を与えることがあるので、注意が必要です。
同系色でまとめたお部屋に個性をプラスするには、アクセントカラーを加えると、単調な空間に変化が生まれます。
アクセントカラーは、メインカラーの中に、目立つ色を少量、ポイントとして配色に加えることで、部屋全体が引き締まります。クッションやテーブルクロスといった、小物で取り入れると失敗が少ないですね。
リノベーションでは、建具を鮮やかな色にしたり、キッチンまわりの壁にタイルをしつらえたり、といった方法で取り入れることも多いです。

事例:https://hikarinobe.com/constructioncase/case_0002/より。白とブラウンで統一された中に、空色のドアを配置することでアクセントに。
スタイルを統一する
もう一つ、部屋の雰囲気を決定づけるのがスタイルです。
スタイルとは、具体的には「木を基調にナチュラルなテイストに」「コンクリートの躯体を見せてインダストリアルな雰囲気に」といった、内装やインテリアの方向性のことです。
リノベーションでは、はじめにスタイルを決めてから、そのスタイルに沿って内装や建具などの素材と色を選んでいきます。
完成した部屋のスタイルと、家具のスタイルがちぐはぐだと、空間に統一感がなくなってしまいます。
部屋がアジアンテイストなら、アジアン家具を選んで配置するというように、家具の素材やブランドも、はじめに決めたスタイルに沿って選んでいくと、失敗がありません。
家具まで含めたリノベーションプラン
家具の選び方、配置の仕方のコツをご紹介してきましたが、やはり「自分で全部やるのは面倒臭い」「センスのいい人にやってもらいたい」という方もいるのではないでしょうか。
ひかリノベでは、家具のコーディネートも承っております。家具配置、家具選びも含めたリノベーションのプランニングが可能です。
リノベーション後に、新しく家具を買うときによくある困りごととして、「部屋と色を揃えたいけど、販売されてる家具は微妙に色味が合わない」「部屋中の寸法をキッチリ測っている時間がない」などがあげられます。
ひかリノベでは、インテリアコーディネーターがコンセプトに合わせた家具選び・レイアウトまで含めたプランが提案可能です。
お気に入りの家具を中心に、内装素材や色を決めていく、といった空間設計も容易です。
また、当社では家具の造作も承っています。オリジナルの家具を作ることも可能です。
リノベーション完成後に、後付けでオーダーメイドの家具を作るとなると、時間も費用もかさみます。壁に造り付けの棚やカウンターを造作する場合など、リノベーションのタイミングで施工をする方が、仕上がりも美しく、時間や費用のコストも抑えられます。
「手持ちの家具をアレンジしたい!」といったご要望にもお応えできますので、ぜひお気軽にご相談ください。
下記の記事は、実際にひかリノベでインテリアコーディネートまで行った事例、家具を主役にした空間デザインの事例、家具造作を行った事例です。
ぜひリノベーションを考える参考になさってみてくださいね。
当社ひかリノベは、オーダーメイドのリノベーションと中古マンション・中古戸建の売買仲介サービスをご提供しています。
家探しからのリノベーションをご希望の方は、物件探しから設計・施工まで。居住中のご自宅のリノベーションは、工事中の仮住まい探しから設計・施工まで、ワンストップでおまかせいただけます。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。