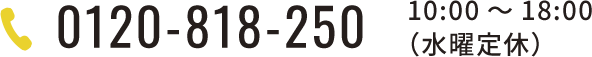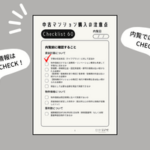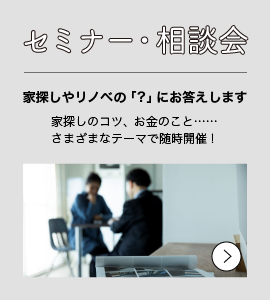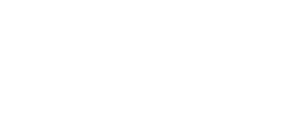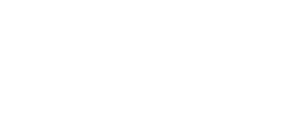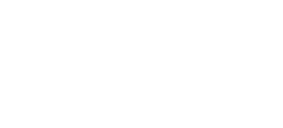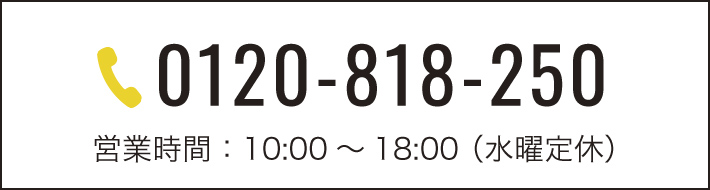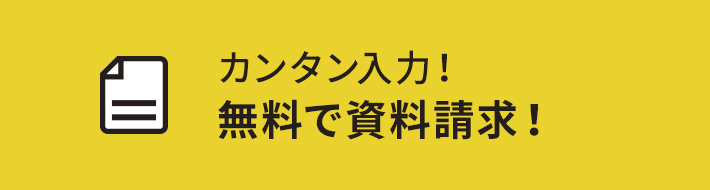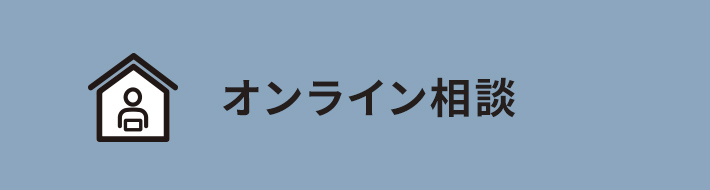ピアノが趣味の人や子どもにピアノを習わせたいと考えている人にとって、自宅にピアノの防音室や防音部屋があるのは、夢の一つではないでしょうか?
そこでこちらの記事では、ピアノに特化した防音対策の方法や防音工事の注意点、工事にかかる費用の目安などをご紹介。
また実際にピアノ防音室へリフォームした施工事例を通して、失敗しないコツや大切なポイントについても解説します。子どもにピアノを習わせたい、気兼ねなく自宅でピアノを弾きたいと考えている方は、ピアノ防音室へのリフォームを検討しましょう。
目次
ピアノの防音対策
ピアノにはグランドピアノとアップライトピアノの二種類があります。音の出る場所はそれぞれ違いますが、いずれも演奏するとなるとかなりの音量になります。
音の大きさ(音量)や騒音を測る指標はデシベル(dB)という単位で表され、数字が大きいほど音量が大きくなります。
こちらは日常の生活音をデシベルで表した一覧です。
| デシベル(dB) | 音量 |
| 0dB | 人間の耳で聴きとれる限界 |
| 20 dB | 小さな寝息程度 |
| 40 dB | 静かな図書館内 |
| 80 dB | 普段の会話 |
| 100 dB | 地下鉄の電車内 |
ピアノの音量は弾く人にもよりますが、一般的に90~95dBあるとされます。これは地下鉄の電車内程の音量で、パチンコ店の店内よりも大きな音です。
それほど大きな音が出るピアノの防音工事は、個人でやろうと思ってもなかなかできるものではありません。
また楽器を演奏する場合、楽器の種類に応じた室内の音の響きを作るのも重要。
音が反響しすぎて練習時に自分の演奏が聞き取れない、上手に演奏できているか分からないというような状態では、せっかく防音室を作った意味がなくなってしまいます。
そういった意味でも防音リノベーションは、防音や音響、楽器についての知識が豊富な専門業者に依頼することをおすすめします。
ピアノの防音室工事の注意点
ピアノの防音室を作る場合には、どのような点に注意すればいいのでしょうか。
防音の専門家に工事を依頼する場合でも、基本的な知識を押さえておくと、工事についての説明が理解できたり、要望を伝えやすくなったります。
ピアノは音域が広い「弦打楽器」の一種。単音が連続して発生する特徴がある楽器です。
また、ピアノは鍵盤につながっているハンマーが弦を打ち、弦の端がつながっている駒が響板に伝わることで、空気を振動させて音を鳴らします。
空気を伝わって聞こえる音(空気伝播音)と、ペダルや弦を打つ時に出る振動の両方が発生するため、防音室工事をする場合はその両方の対策が必要になるのです。
ピアノの低音に注意
ピアノは高い音から低い音まで、非常の音域が広い楽器です。
高音も低音も両方しっかり遮音できる防音室を作らないと、「ピアノを弾く音がうるさい」という苦情が寄せられてしまうかもしれません。
とくに注意が必要なのは低音。
低音は高音に比べて音の波長が長くなるため、その波が防音壁の厚みに収まりきらないと音が壁を貫通しやすくなってしまいます。
高い音は遮音できても、低い音が外にもれてしまう可能性があるのです。
低音を遮音するには、下地や表層材に低音域の吸音や遮音に優れた吸音ボードを使用する方法があります。
具体的には、遮音性能を示すD(Dr)値が、D-50~D-55を目標に設計するとよいでしょう。
ピアノの振動に注意
ピアノを弾くと空気を伝わって聞こえる音だけでなく、ペダルや弦を打つ時に出る振動も発生します。ピアノ防音室の工事では、この振動の対策も必須になります。
ピアノ本体から発せられた振動は、ピアノの脚から床に伝わって、床を通して下の階の部屋や隣の部屋に音として伝わります。こうした音のことを「固体伝播音」といい、伝わる経路が複雑で、空気を伝わる「空気伝播音」よりも防音が難しい特徴があります。
ピアノ防音室を作る場合、この固体伝播音を外に漏らさないための対策が欠かせません。固定伝播音は壁や床を伝って移動するため、既存の部屋の内側にもう一つ箱を作り、躯体への振動を遮断する浮遮音構造の防音室がおすすめです。
ピアノが壁から離れている場合は床に高さのある「防振架台」を設置することでも、ピアノの脚から床に伝わる振動を防ぎ、防音効果を高めることができます。
床の防振設計については、こちらの記事で詳しく解説しています。ピアノ防音室を作る際の参考にしましょう。
防音工事の費用の目安
ピアノ防音室を作るときには、費用がどのくらい掛かるかも気になる所です。こちらではRCマンションに防音室を設置した時の費用の目安を紹介します。ユニットタイプの防音室もありますが、こちらはオーダーメイドの防音室の価格となります。
開口部を除いた複合遮音性能:D-65~70で施工します。
※建具・サッシのサイズおよび仕様により金額の変動があります。
| 既存面積(畳) | 既存面積(㎡) | 価格(円) |
| 3 | 5.0 | 280万 |
| 4 | 6.6 | 330万 |
| 5 | 8.3 | 360万 |
| 6 | 9.9 | 390万 |
| 7 | 11.6 | 420万 |
| 8 | 13.2 | 440万 |
※生ドラム仕様は施工不可(電子ドラムは可)
グランドピアノの防音室を作る場合、3畳ほどの大きさでもギリギリ入れられますが、楽譜に書き込みする小机を脇に置いたり隣で指導してもらうには、一回り大きな4.3畳以上のサイズが必要です。
アップライトピアノは3畳サイズの防音室がおすすめです。
既存の部屋の大きさやピアノの種類、予算に応じて防音室の広さを決めていきましょう。
ピアノの防音室事例
こちらでは実際にピアノ防音室を作ったリフォーム事例を参考にしながら、実際に施工する場合のポイントやアイデアを紹介していきます。
case.01「音も雰囲気も柔らかなピアノ音楽教室」

白を基調とした防音室。ピアノ音楽教室のために施工されました。
以前はピアノの音があまり響かないデッドな吸音率だったため、今回は思うようなピアノの音を鳴らせられるような音響設計に。
壁紙には自然の鉱物や粘土から作った「エコカラット」を使用。消臭効果や調湿効果があるので、お部屋の匂いが気にならず木製のピアノのコンディションを整えるのにも役立っています。また表面の細かい凹凸は音の拡散に役立ち、ピアノの音色を一層美しく聞かせるメリットも。
親御さんが座って見られるソファやちょっとした作業に便利な作業机もあり、使い勝手の良いピアノ室に仕上がっています。
case.02「和室をリフォームし華やかなピアノ室へ」

こちらはマンションの和室をピアノ室にリノベーションした事例です。将来ピアノ教室を運営することを考え、ドアと掃き出し窓の両方から出入り可能なようにも工夫しています。
ピアノから出る振動を構造躯体に伝えないよう浮遮音構造でリフォームし、ドアや窓といった開口部にも防音性能のある建具を取り付けました。
気密性の高い防音室のデメリットとなりがちな換気のしにくさは空調の設置で解消しています。
また施工時に配線用の配管を壁と天井に埋め込んでいるので、オーディオルームやシアタールームとして使う時も電源を確保するのに苦労する必要がありません。
まとめ
ピアノ演奏のための防音室を作る場合は、空気を伝わって耳に入る音だけでなく床に伝わる振動に対する対策も必要です。また低い音から高い音までの音域が広いピアノを思いっきり演奏するためには、遮音しにくい低音域もしっかりと外に伝わらない対策が求められます。
そのためには、防音工事に特化した専門業者によるリフォームが欠かせません。防音工事は建築や建物の構造のことだけでなく、音響や楽器の鳴り方についても詳しくないと、思うように防音できなかったり、楽器の音色が良く聞こえないことも。
マンションのスケルトンリノベーションを得意とするひかリノベでは今回、防音工事のスペシャリストである昭和音響さんと提携。 昭和音響さんは一般住宅の防音工事だけでなく、ライブハウスやクラブなどの防音工事も手掛けているので、プロのミュージシャンにも認められた防音技術があります。
工事完工後は約束した遮音性があるかの音圧確認を実施しているので、結果に満足すること間違いなし!
マンションの防音工事をするには壁や床、天井を解体するスケルトンリノベーションと一緒にするのがベスト。マンションの防音室リフォームも、ぜひひかリノベにお任せください。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。