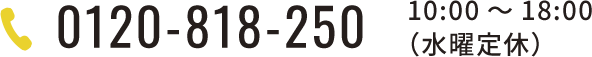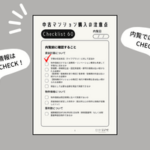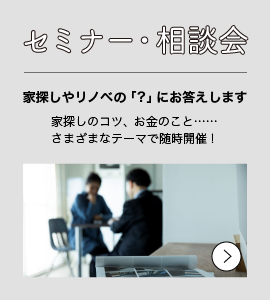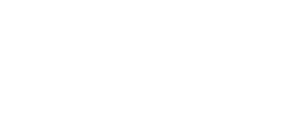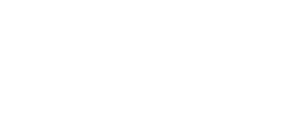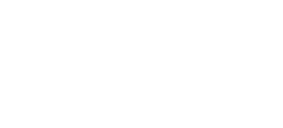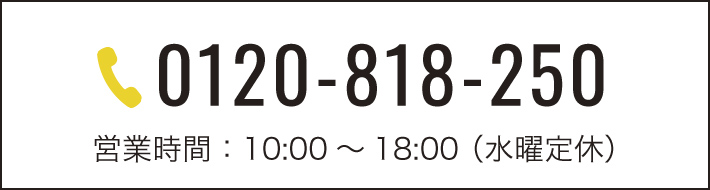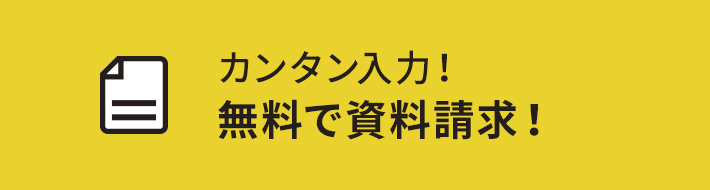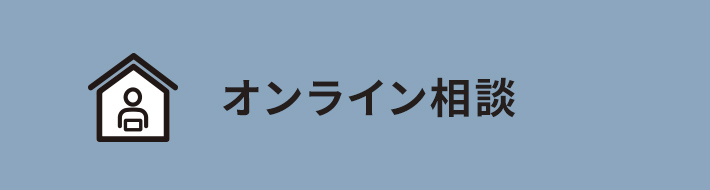断熱リフォームで、夏の暑さや冬の寒さが気になる部屋も快適に。住まいの断熱性能が向上すれば、冷暖房効率も高まり、電気代の節約にも繋がります。
この記事では、工事方法と費用の相場、注意点を解説します。
ここ数年、断熱・省エネリフォームの補助金や優遇税制が充実しています。住まいのリフォームをお考えの方は、断熱リフォームをうまく組み合わせることで、お得に工事ができるかもしれませんよ。
目次
マンションの断熱リフォームの工事方法
マンションの断熱リフォームとは、具体的にどんな工事方法があるのでしょうか。
まず前提として、マンションの場合、外壁や窓サッシなどは共用部分にあたるため、個人でリフォームはできません。そのため専有部分である室内からの壁断熱や、内窓の設置、あるいは(管理組合の許可を得たうえで)窓サッシのカバー工法といった工事が選択肢となります。
壁の断熱~乾式断熱と湿式断熱
マンションの外壁は共用部分にあたるため、壁の外側に断熱材を設置する工事(外断熱)はできません。そのため、室内側に断熱材を設置します(内断熱)。
断熱材には、発泡スチロールなど板状の断熱材(乾式断熱)と、スプレーガンで吹き付ける泡状の断熱材(湿式断熱)があります。
乾式断熱は施工が比較的容易で、費用も湿式断熱にくらべ安価な点がメリット。
デメリットは、梁や柱の凹凸が多い物件では施工が難しい場合があったり、継ぎ目に隙間ができると気密性が低くなり、充分な断熱効果が得られない可能性があります。
湿式断熱は壁に隙間なく断熱材を充填でき、梁や柱の凹凸があっても高気密に仕上がるのがメリットです。
デメリットは、トラックにコンプレッサーを積み、ホースを繋いで噴射するため、物件の立地条件によっては施工できません。また高層階の場合も、ホースが届かなかったり、泡を圧送できないため、施工できません。
窓の断熱~内窓設置とカバー工法
窓サッシも共用部分にあたるので、勝手に交換はすることはできません。
そのためマンションの窓断熱でよく採用されるのが「内窓」の設置です。既存の窓の内側にもうひとつサッシを取り付ける工事で、二重窓・二重サッシとも呼ばれます。
もしくは、事前にマンションの管理組合の許可を取り、既存のサッシ枠の上に新しい窓枠を被せる「カバー工法」という方法もあります。
内窓設置は、管理組合の許可も不要で、カバー工法より安価にできる点がメリットです。
デメリットは部屋が狭くなること、窓が二重になるため開閉が面倒になり、掃除の手間も増えることです。
カバー工法は、既存のサッシに歪みや隙間が生じている築年数が古めの物件ではとくに効果的。既存の外窓に不具合が残っている場合、内窓を設置しても、断熱効果が充分に得られません。こうした場合は、内窓設置よりも既存サッシの歪みや隙間を覆ってしまうカバー工法のほうが効果を発揮します。
デメリットは、既存サッシのうえから枠を被せるため、窓の開口がひと回り小さくなることです。
マンションの断熱リフォームの費用相場
リフォームの費用は、規模や内容によって異なります。ここでは、窓廻りのリフォームのみの場合と、壁の断熱施工も行う場合に分けて解説していきます。
窓廻りのリフォームだけ行う場合
開口部(窓やドア)は、建物の中でもとくに熱の出入りが大きい部分。冬の暖房が逃げる原因箇所は窓からが58%、夏の冷房はさらに高く73%だという研究があります。
(※一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会)
したがって断熱リフォームを検討するにあたっては、まずは窓の断熱を考えたいところ。
内窓施工も、カバー工法も、工期は基本的に1日で、比較的気軽に実施できます。
工事費用は、内窓工法の場合、窓の大きさとガラスの種類(単層ガラスか複層ガラスか)で異なります。断熱性能が高い「複層ガラス」を採用した場合、腰高サイズ2枚立てで4~6万円程度、掃出窓2枚立てで8~10万円程度が目安となります。
※金額はあくまで目安です。実際の費用は、物件の状況や併せて行う工事によっても上下します。
カバー工法では窓の大きさとガラスのほか、サッシの種類によっても金額が異なります。断熱性能が高い「アルミ樹脂複合サッシ」「LOW-E複層ガラス」を採用した場合、腰高サイズ2枚立てで20万円~、掃出窓2枚立てで30万円~が目安となります。
※金額はあくまで目安です。実際の費用は、物件の状況や併せて行う工事によっても上下します。
壁の断熱も行う場合
壁の断熱も行う場合、既存の壁や床を壊して躯体を剥き出しにした「スケルトン状態」にして、断熱材を設置することになります。
内装の一新や間取り変更を伴うフルリフォームの一環としておこなうのが一般的。
フルリフォームの費用の目安は下表のとおり(当社ひかリノベも加盟しているリノベーション会社ポータルサイト『SUVACO』調べのデータです)。
| 工事内容 ※マンション 60㎡を想定 |
予算 | ||
| 800万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
| 水まわり設備の取り換え | ◎ | ◎ | ◎ |
| 内装(床、壁、天井)の一新 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 間取り変更 | △ | ◎ | ◎ |
| 造作家具や素材へのこだわり | △ | △ | ◎ |
| 断熱工事 | × | × | ◎ |
(※出典:SUVACO)
60㎡の標準的なマンションの一室で、水廻り設備の交換・内装の刷新・間取り変更を行う場合は1,000万円~。さらに断熱工事を行う場合は1,200万円~。造作家具も取り入れる場合は1,500万円~が目安となります。
工期は、内容にもよりますがおよそ3ヶ月~4ヶ月。工事中は、既存の部屋を一旦解体するため住める状態ではなくなりますので、仮住まいが必須となります。
マンションの断熱リフォームの注意点
マンションの大規模リフォームは、戸建てとは異なる、マンション特有の注意点があります。ここでは特にマンションの断熱リフォームにおいて、注意すべきポイントについて解説します。
管理規約による制約
前提として、マンションのリフォームは管理規約の制約を受けます。共用部分は、勝手にリフォームができません。
たとえば、窓サッシは共用部分なので、カバー工法による窓断熱は、管理組合の許可が必要となります。
壁の湿式断熱は、専有部分の工事ですが、コンプレッサーを積んだトラックの駐車場所や時間が問題となる可能性があるので、やはり事前に管理組合に確認が必要です。
必要な工事は物件ごとに異なる
どこまで断熱リフォームを行うべきかは、物件によってケースバイケースです。角部屋や最上階と、中間階で左右も隣戸に挟まれている場合では、必要な工事は異なります。
最上階では壁だけでなく天井の断熱が重要になりますが、中間階の場合は、上下に住戸があるため、屋外のような温度差は生じないため、天井断熱の優先順位は低くなります。
角部屋と、左右が隣戸に挟まれている部屋の場合も同様です。
リフォーム会社(リノベーション会社)の設計担当とよく相談し、「この物件に必要な工事は何か」を個別に検討することが大切です。
マンションの断熱リフォームに使える補助金
近年は、断熱リフォームに使える補助金や減税制度が充実しています。
窓の断熱改修と壁の断熱施工に使える補助金として「子育てグリーン住宅支援事業」、内窓設置のみの場合でも使える補助金として「先進的窓リノベ2025事業」、カバー工法や内窓設置に使える補助金として「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」、「既存住宅における省エネ改修促進事業」といった制度が用意されています。
補助を受けるためには工事方法や利用する製品などに一定の要件があるので、この点もリフォーム会社(リノベーション会社)の担当者によく確認しましょう。
下記はリフォームやリノベーションにつかえる補助金・優遇税制の特集記事です。
補助金や優遇税制に興味のある方は、ぜひこちらも併せてご覧ください。
まとめ
この記事では、マンションの断熱リフォームのポイントを解説しました。
ひかリノベでは、今回ご紹介した「内窓施工」「窓サッシのカバー工法」「各種壁断熱」といったリフォームに対応しております。自宅の寒さや暑さがきつい、カビや結露に悩んでいる、光熱費が高いなど、住まいの断熱性でお悩みの方は、ぜひひかリノベまでご相談ください。
また、補助金や減税制度のご利用もサポートいたします。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。