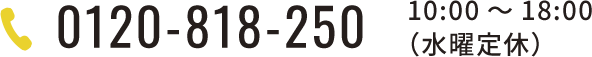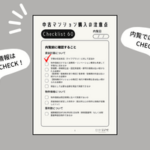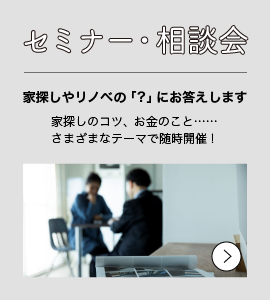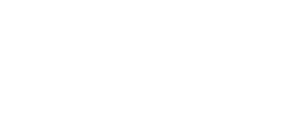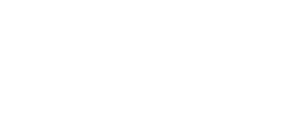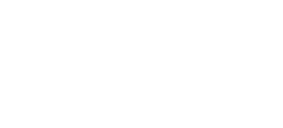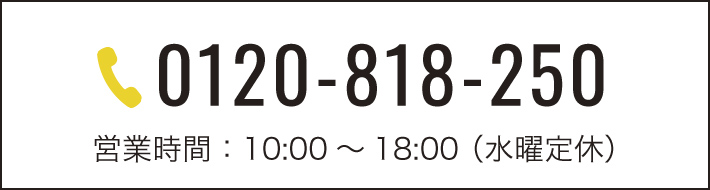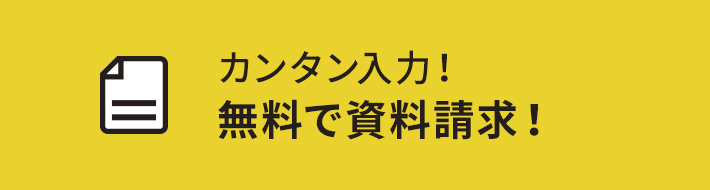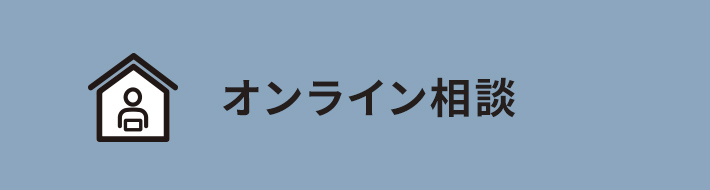部屋の中の湿度が低い状態では、乾燥して肌やのどを痛めてしまう可能性もあり、人間の健康面への悪影響が心配です。
反対に湿度が高いと、カビやダニが増えやすく健康への影響だけでなく、建物への悪影響も。
この記事では、適正な湿度は何%なのか。また、湿度を快適に保つためにはどんな方法があるのかを解説していきます。
目次
室内の湿度は何%が適正?
人間が快適に過ごせる湿度の目安は、40~60%だといわれています。とはいえ温度との関係もあるので、季節によって適切な湿度の値は変わってきます。
外気温が高くなり、湿度も高い夏場は、室温25~28℃で湿度50~60%を保つのが良いとされています。
逆に外気温が低く、室内は暖房等で乾燥しやすい冬は、室温18~25℃で湿度40~50%が理想的です。
(データ出典:東京都福祉保健局『健康・快適居住環境の指針』)
湿度は高すぎても低すぎてリスクがある
湿度は、高すぎても低すぎても部屋の悪影響を与える可能性があります。具体的にどんな影響があるのか見ていきましょう。
湿度が高すぎる部屋のリスク~結露・カビ・シックハウス
湿度が高すぎる部屋に起こる最大のリスクは、カビやダニです。カビやダニは、湿度50%以上になると動きが活発になり、60%を超えると急激に数が増えていくといわれています。ダニはカビを餌にするので、カビもダニもどんどん増えていく悪循環に。
(データ出典:文部科学省『カビ対策マニュアル』)
カビやダニは、アレルギーの原因となってアレルギー性鼻炎などを引き起こしたり、アトピーを悪化させたりすることにつながります。さらにシックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒドなど)も、湿度が高くなるほど空気中の濃度が高まっていく傾向に。
湿度の高い季節は、気圧も大きく変化しやすいので、自律神経失調症のリスクも。じめじめとした湿度の高い部屋は、そこに住んでいるだけで、人間の健康に悪影響を与えてしまうのです。
湿度が低すぎる部屋のリスク~感染症・肌荒れ・静電気
では湿度が低い(40%以下の)環境下では、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
インフルエンザや新型コロナなどのウイルスは、湿度が低い環境で活性化する特性を持っています。そのため風邪やインフルエンザといった病気(感染症)にかかるリスクは高くなります。
肌も、乾燥するとバリア機能が低下して荒れやすくなり、かさつきや痒みを引き起こすほか、シミやシワの原因になることも。とくに乳幼児は肌のバリア機能が完全ではないので、赤ちゃんのいるご家庭では湿度管理に気を遣いますね。
また、冬場は静電気が気になる方も多いはず。静電気は空気中の水分を通して放出されるため、乾燥した空間では静電気の逃げ道がなくなります。それによって、何かを触った拍子に電気が流れ、痛みを感じるのです。たまった静電気は、ホコリも引き寄せてしまいます。
適正な湿度を保つには?
湿度は、季節や気候によって変動します。適切な湿度を保つためにはどのような方法があるのかを紹介していきます。
ジメジメする季節に~湿度を下げる方法
外気の温度・湿度が高まる梅雨時〜夏場にかけては、次のような湿度を下げる工夫が効果的です。
- 換気を行う
- エアコンを除湿運転する
- 除湿器を活用する
- 洗濯物は部屋干ししない
お風呂や料理、洗濯といった日常の習慣も、室内の湿度が上昇する原因になり得ます。とくに浴室の扉は開けっ放しにしないようにしましょう。
一戸建てや、マンションでも低層階は、地面に近いので湿度が高くなりやすいです。反対に、高層階の住戸は乾燥しやすい環境にあります。
水はけが悪い土地や、近所に川がある、緑の多い地域の近くにお住まいの方は、こまめな換気や除湿を心がけるよう意識してみてください。
乾燥が気になる季節に~湿度を上げる方法
外気の温度・湿度が下がる冬〜春にかけては、暖房によって乾燥が進みやすくなるため、次のような方法による適度な加湿調整が必要です。
- 加湿器を使用する
- 洗濯物を部屋干しする
- 濡れたタオルを干しておく
- カーテンを霧吹きで湿らせる
- 入浴後、浴室のドアを開けたままにする
とはいえ、冬でも湿度が高すぎるとカビが発生する可能性があります。とくに窓廻りやカーテン付近は、結露が発生しやすくなります。カビやダニの原因になってしまうので、加湿のし過ぎには注意しましょう。
とくに、暖房として石油ストーブやガスファンヒーターをお使いの方は要注意。石油ストーブやガスファンヒーターは大量の水蒸気を出すため、気温とともに湿度も上昇します。
リフォームで湿気に悩まない住まいづくり
湿気のお悩みは、リフォームでも軽減できます。ここでは、風通しのよい快適な住まいをつくるリフォームのコツを紹介します。
風通しのよい間取り
個室が多い間取りは空気の流れが悪い場所ができやすく、陽当たりの悪い北側の個室は気温が低く、相対湿度が高くなりがちです。
しかし換気しやすく家全体を空気が通り抜けるような間取りにすることで、特定の部屋だけがじめじめするような事態を改善できます。
室内窓で風の巡る住まいに
換気の面からも、空気の流れをきちんとつくることは重要です。
風通しの悪い個室には、室内窓をつけるのがおすすめ。室内窓を開け放っておけば、梅雨時など多湿な時期でも湿気がこもりにくく、個室を収納として使うような場合にもおすすめです。
調質建材で湿度をコントロール
「調湿建材」とは、湿度が高いときには水分を吸い、乾燥しているときは水分を放出する機能がある建材のこと。代表的なものとして、ゼオライトや珪藻土、エコカラットなどが挙げられます。
多くの調湿建材には、臭いやホルムアルデヒドなど化学物質を吸収してくれる効果もあるので、お部屋の快適さをさらに高めてくれるでしょう。調湿建材については、下記の記事で詳しく特集しています。ご興味のある方は、ぜひ下記もあわせてご覧ください。
断熱施工で室温を一定に
湿度は温度と相関関係があり、気温が高くなるほど空気の中に含まれる水分(水蒸気)は増えるため、暖かいと相対的に乾燥しやすく、寒いとじめじめしやすくなります。
壁や天井、床に断熱材を入れたり、内窓をつけたりして断熱性を高めると、年間を通じて室温・湿度が変化しにくくなります。断熱施工をすると結露も発生しにくくなり、冷暖房効率が向上して光熱費も安くなるので、一石二鳥ですね。
湿気に悩まない物件探しのコツ
物件の立地条件によっても、湿気が貯まりやすくなります。例えば海沿いや川沿いの物件では、湿った空気の影響を受けやすくなります。また水はけの悪い地盤のエリアに立つ物件も、地面から近い1階の部屋に湿気が貯まりやすいです。
立地以外にも、敷地内に雑草が放置されている物件は要注意。雨上がりに地面の渇きが遅いので、湿気が貯まりやすくなっています。管理状態を確認する上でのバロメーターにもなるので、内見の際は注意して見てみてください。
また、外からはわからなくても、室内の壁や押し入れがカビ臭い物件も要注意です。何らかの原因で、湿気が貯まりやすい状態になっているのかもしれません。
おわりに
湿度は高すぎても低すぎても、住宅やそこに住む人の健康にリスクを生じさせる可能性があります。気温に合わせた適正湿度にする方法はいくつもあり、簡単に実践できるものも多いので、気軽に試してみましょう。
もし今お住いの家やこれから購入しようとする物件に、湿気の問題があるときには、風通しの良い間取りへの変更や、調湿建材を使ったリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。
当社ひかリノベは、ひかリノベでは、オーダーメイドのリノベーションと中古マンション・中古戸建の売買仲介サービスもご提供しています。みなさまのご希望や住まいの特性に応じて、風通しのよい間取り、調湿建材のご提案など、換気にも配慮したリノベーションをご提供します。
家探しからのリノベーションをご希望の方は、物件探しから設計・施工まで。居住中のご自宅のリノベーションは、工事中の仮住まい探しから設計・施工まで、ワンストップでおまかせいただけます。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。