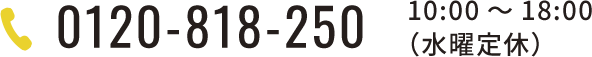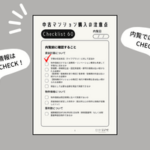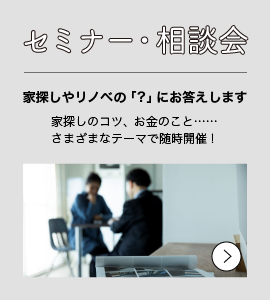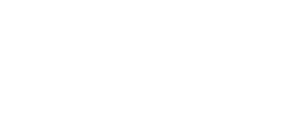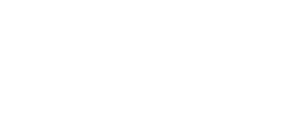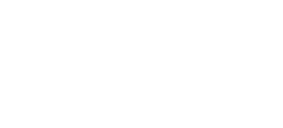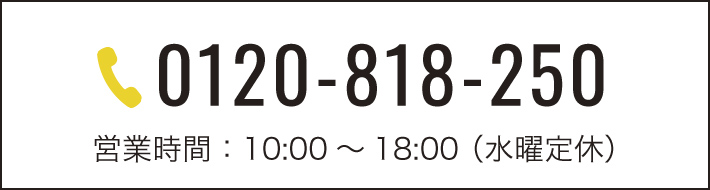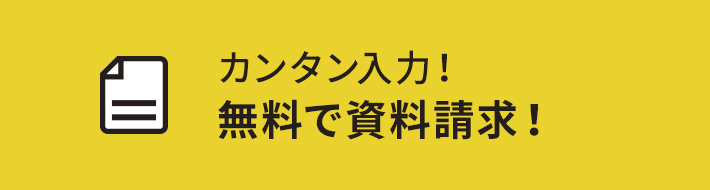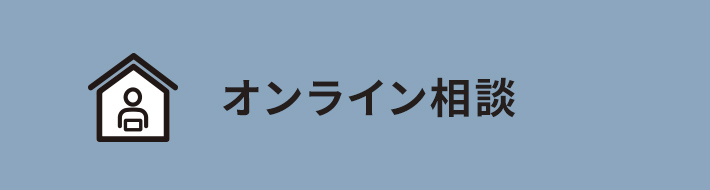中古物件のリノベーションは、建物の構造やマンションの規約によって、出来ない工事もあります。
「水廻りの間取りを変更したかったが出来なかった」「壁を壊して広いリビングにしたかったが出来ないと言われた」etc…
また「思ったより費用がかさんでしまい節約できなかった」などの声も耳にします。
こうした失敗を防ぐためには、一体どのような点に気をつけたら良いのでしょうか。
今回は、あとで「こうしておけば良かった…」と後悔しないために、予算を抑えるコツ・物件選びのポイント・プランニングの考え方・業者選びのポイントなど、工事の前に知っておきたい知識をケーススタディでご紹介します。
2017年7月18日初出→2020年2月18日更新→2021年5月6日更新
目次
リノベーションで失敗しやすいポイント
物件の購入やリノベーション会社の選択を誤ると、完成した家に不満が残ってしまったり、後悔する可能性も考えられます。
失敗につながりやすい原因を整理すると、大きく次の4つに分けられるようです。
①予算・資金計画の失敗
②物件選びの失敗
③設計・プランニングの失敗
④会社選びの失敗
次の章から、①〜④それぞれの具体的なケーススタディをご紹介します。
予算・資金計画の失敗事例と回避策
まずは、誰しも気になる資金面の問題からみていきましょう。
居住中のご自宅や、相続した物件、ご実家といった所有物件のリフォームは、工事費用だけ考えれば問題はありません。
しかし、中古を買ってリノベーションの場合は、物件購入費用とリノベーション費用の総額を考えなくてはいけません。
工事にいくらかかるか把握できないうちに物件を買ってしまうと、「もっとリノベーションしたいところがあったのに、予算が足りなくなってしまった」という事態に陥ってしまうリスクがあります。
物件にお金をかけすぎてリノベ費用が足りない
Case1
リノベーションの計画を立てる前に物件を購入したが、思ったよりリノベーションにお金がかかることが発覚。予算が足りなくなって、多くのリノベーション箇所を我慢することに……。
中古を買ってリノベーションの場合は、物件購入費用とリノベーション費用の総額を考えなくてはいけません。
リノベーション費用の目安は、フルリノベの場合で㎡単価15~20万円ほどが中央値ですが、使用する内装部材や設備のグレード、既存の物件の状況によっても幅があります。
ですから「まず物件を買ってからリノベ」は失敗のもと。「まずはリノベの見積もりを取ってから物件探し」が正解です。
物件購入の前にリノベーション費用がわかっていれば、住宅ローンで「物件代金+リノベ費用」をまとめて借入できる金融機関も多いです。
リフォームローンは住宅ローンに比べ、金利も割高。支払金額を最終的に抑えるためにも、「物件の前にリノベ」が鉄則です。
費用をおさえるために妥協してしまった
Case2
プランニングを進める中で、リノベーションの希望が増えていった。改めて見積もりを出してもらったら、大幅に予算オーバー。費用を抑えるために全体のグレードを落としたが、妥協したことに後悔が残った。
このケースは、物件購入やリノベーションプランを練る段階でのつめの甘さが原因となってしまったようです。
購入前にリノベの概要を決める段階で、すべての希望を整理できていれば良いのですが、購入後の細かな仕様決めを進める中で、新たな希望が出てくるのも、珍しいことではありません。
予算内で理想の住まいを完成させるためのポイントは、最初の見積もりの段階で「新しい住まいで絶対に実現したいこと」を決めておくこと。
譲れない部分と、出来ればこうしたいという部分――「アイランドキッチンは譲れないけど、お風呂はグレードを落としてもOK」というように優先順位を整理しておくことです。
優先度順をつけておくと、プランを詰めていく中で判断に迷ったときの指針になります。
物件選びの失敗例と回避策
リノベーションは既存の枠組みを利用するため、建物の構造によっては出来ない工事もあります。
また、中古物件は築年数が古いほど安価になりますが、経年劣化が進んだ物件は、その分多くの補修工事が必要になる可能性も。
物件選びの段階で失敗を防ぐためのポイントを見ていきましょう。
購入したマンションが間取り変更ができない構造だった
Case3
中古マンションを購入後、設計事務所にリノベーションを依頼したが、そこで建物の構造や規約により、水回りの移動や床材の変更が出来ないことが発覚。思い通りの工事が出来なかった。
建物は耐震のために抜けない柱や壁があり、その存在が間取り変更の障壁となる場合があります。
とくにマンションの場合、間取り変更がある程度自由にできる「ラーメン構造」と、撤去できない構造壁を持つ「壁式構造」の二種類があります。
古いマンションはとくに壁式構造が多く、場合によっては希望の間取りにできないことがあります。
また、マンションでは配管をまとめて通している空間があり、このパイプスペースは動かすことができません。
パイプスペースの位置によっては、水廻りの移動が制限されることも。
さらに、マンションには住民がその資産価値を維持しながら快適に暮らすためのルールである「管理規約」があります。
また物件によっては、専有部分である住戸内についても、防音のために床材が制限されている場合も。
こうした制約によって思い通りのリノベーションができないという失敗も、物件を決める前におおまかなプランを決めておき、計画に合わせて物件を選ぶことで回避できます。
物件購入からリノベーションまでを一括しておこなっているワンストップのリノベーション会社は、プランに合わせた物件選びが仕組み化されており、このような失敗が起きにくいのでおすすめです。
物件購入後、見えない部分の劣化が判明した
Case4
安さを理由に築古物件を購入。その後、配管や下地の見えない部分にかなりの劣化があることが発覚した。結果、修繕箇所にかかる費用がかさみ、当初の予定より節約できなかった。
物件は築年数が古いほど安くなりますが、その分配管や下地の経年劣化が進んでいる可能性も。予算は補修費用も込みで考えなくてはいけません。
戸建てのリノベーションはマンションにくらべ自由度が高く、雨漏りの修繕や耐震補強も可能ですが、工事の範囲や内容と価格は比例します。
とくに築年数の古い戸建ては、断熱性能や耐震性能といった住宅としての基本性能に課題がある場合が多いです。
物件価格が安いからといって、古くて性能面で問題の多い物件を購入してしまうと、修繕費用で予算をオーバーしてしまうリスクも。
リノベーションの設計や施工管理担当に、物件や図面を見てもらうなど、建築知識のあるプロの目で補修が必要な部分を判断してもらってからの購入が得策です。
設計・プランニングの失敗例と回避策
プランニングは決めることがたくさんありますね。
「木を基調に、ナチュラルなテイストにしたい」「オープンキッチンに憧れる」など、抽象的な希望はあるけれど、具体的な設備や内装部材、照明やコンセントの数と位置などは、どのように決めていけばよいのか……と悩む方が多いです。
細かな部分の仕様決めは、どのように考えてゆくと失敗しないのでしょうか?
実際の生活をイメージせずプランを決めてしまった
Case5
収納の量やコンセントの数など、よく考えずにリノベーション会社にすすめられるがまま決定してしまった。しかし実際生活してみたら、家の中に使いにくいところがたくさん出てきてしまった。
ハウスデザインのプロである設計担当者と相談しながら決めていくことになりますが、快適で暮らしやすい家をつくるポイントは「ライフスタイルから仕様を決めていく」ということです。
家族の生活時間帯や、身長、各部屋で使用する家具家電など、暮らしの希望があれば、設計者はそれを叶えるデザインを提案できます。
まずはどんな暮らしがしたいか、新しい家で暮らす自分や家族の姿をイメージしましょう!
とくに完成後に不満が出てきやすいのが、収納の場所や大きさです。荷物は生活とともに増えるもの。いま必要な量に対して、余剰が出るくらいでちょうどいいと考えましょう。
全体のバランスを考えず当初の要望にこだわった結果……
Case6
キッチンは作業台やシンクが大きいほど使い勝手がよいと思っていたが、かえって動線が遠くなり、使いづらくなってしまった。スペースに対して大きすぎるキッチンを入れたせいで通路も狭く、設計担当者のアドバイスを聞けばよかったと後悔……。
希望がはっきりしている時こそ、デメリットが見えにくかったり、つい「無理をしてでも!」と考えてしまいがちなので注意。
まずはその設備や間取りを取り入れる目的を考えましょう。
とくにキッチンは、広い作業台やシンクを希望する方が多いですが、キッチンが大型になればなるほど、動線も長くなります。シンクとコンロを分けて二列型にするなど、さまざまな方法がありますから、まずはどんな使い方がしたいかを設計担当に伝え、アイデアを提案してもらうと良いでしょう。
会社選びの失敗例と回避策
リノベーションやリフォームは、信頼できる請負先を探すことから始まります。
価格やネームバリューだけで会社を決めてしまうと、完成後に問題が発覚することも少なくありません。
「デザイナーとセンスが合わなくて、理想とかけ離れたデザインの家になってしまった」「完成した家の施工に雑な部分や欠陥があった」
こういった請負会社とのトラブルを防ぐにためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
デザイナーとセンスが合わない
Case7
有名な会社だからと、よく考えずに依頼した。デザイナーとセンスが合わない気がしたが、修正を重ねなんとか着工。完成したら、やはりイメージと違う仕上がりになってしまった。
会社名や価格だけで請負先を決めず、複数の会社の資料を請求したり、HPで過去の施工例を見て、自分のセンスと合う会社を吟味することが重要です。
マンションのリノベーションが得意・一軒家のリノベーションが得意・モダンな雰囲気の事例が多いなど、会社やデザイナーの得意分野をリサーチして、自分と合った会社を見つけましょう。
見積もりは価格だけでなく「こちらの要望をきちんと理解してくれるか」「提案されたプランの内容はどうか」といった点をよく確認することが大切です。
住み始めてからの保証がない
Case8
完成した家に住み始めて、たったの2週間で配管の水漏れが発覚。「欠陥工事では…」と不安になったが、相談場所が分からない。
リノベーションの完成後に予想しない問題が発覚することもあります。
「この会社なら大丈夫」と安心せず、もしもの場合に修理や工事のやり直しに応じてくれるのか、保証の範囲をあらかじめ確認しておきましょう。
リノベーション工事の不具合の保証は、会社ごとの工事保証のほか、適合リノベーション住宅・リフォームかし保険といった第三者機関の保証システムがあることを知っておく。ただし、対応している会社とそうでない会社があるので注意が必要です。
(※ひかリノベでは自社保証・適合リノベーション住宅・リフォームかし保険のほか、住宅設備機器の延長保証にも対応しています)
まとめ
中古住宅をリノベーションする際は、リスクやデメリットについて十分理解しておくことが重要です。
とくにマンションのリノベーションでは、集合住宅ならではの制約や決まり、できないことがあります。
たとえば耐震補強。木造戸建の場合は構造計算によって可能ですが、マンションの場合は個人で出来る工事の範囲を超えてしまいます。
心配な方は、新耐震の物件や、耐震基準適合証明を受けた物件に絞って探されると良いでしょう。
もっとも、地震へのつよさは耐震性能だけでなく、地盤も重要な要素です。
地域の地盤の特性、また水害などの災害のリスク全般は、ハザードマップで調べることができます。
このように、リノベーションには出来ること出来ないことがあり、この点を考慮して物件を選ぶことが大切です。
当社ひかリノベでは、「はじめにプランの概要を決めてから物件を選ぶこと」「ライフスタイルのヒアリングを詳細に行うこと」「自社保証のほか第三者機関の保証・保険に対応すること」など、今回ご紹介してきたような失敗を未然に防ぐ仕組みをとっています。どうぞ安心しておまかせください。
当社ひかリノベは、オーダーメイドのリノベーションと中古マンション・中古戸建の売買仲介サービスをご提供しています。
家探しからのリノベーションをご希望の方は、物件探しから設計・施工まで。居住中のご自宅のリノベーションは、工事中の仮住まい探しから設計・施工まで、ワンストップでおまかせいただけます。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。