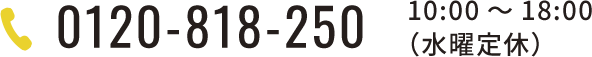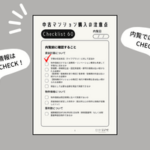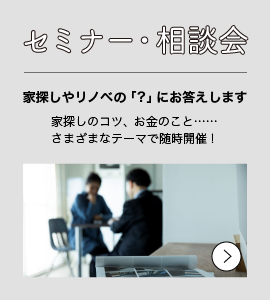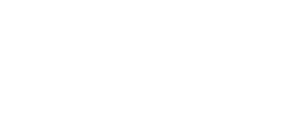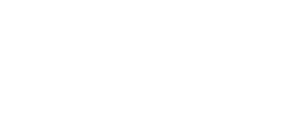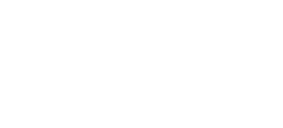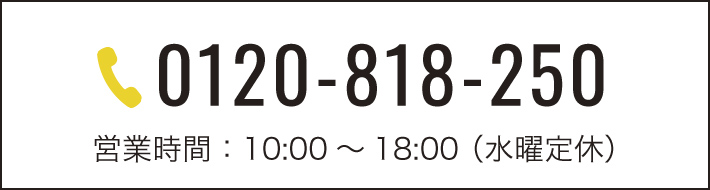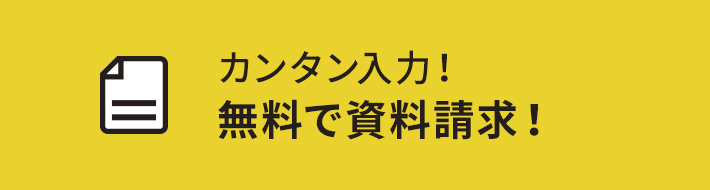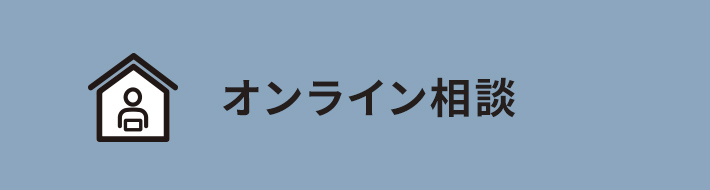所有しているマンションを売却して利益(譲渡所得)を得た場合、所得税や住民税がかかります。あらかじめ「いくら課税されるか」を知っておかなければ、住み替えの資金計画も立てられませんね。
じつは、自宅として住んでいるマンションを売却する際には、さまざまな特例や軽減措置が用意されています。せっかく用意されている節税手段、活用しない手はありません。
この記事では、自宅マンションの売却によって得た利益にかかる所得税の計算方法や、軽減制度といった、「マンション売却と税金」についての基礎知識を解説します。
目次
マンションの売却にかかる税金
購入したときの値段よりも高い価格でマンションが売れると、得た利益(譲渡所得)に対して「所得税」と「住民税」がかかります。
さらに、2037年までは、「復興特別税」として所得税が2.1%上乗せとなります。
また、利益(譲渡所得)の有無に関わらずかかる税金として、売買契約時には「印紙税」が、登記には「登録免許税」がかかります。
これら物件売却に際してかかる税金を、下表にまとめました。
何を・いつ・どのように支払うのか、いま一度確認してみましょう。
| 税の種類 | 支払い時期 | 支払い方法 | |
| 利益が出なくてもかかる | 印紙税 | 売買契約 | 印紙で納付 |
| 登録免許税 | 登記 | 印紙で納付 | |
| 利益が出た場合にかかる | 所得税 | 確定申告 | 振込・振替 |
| 住民税 | 翌年6月頃から4分割で納付 | 納付書で現金納付 | |
| 復興特別税 | 確定申告 | 振込・振替 |
「譲渡所得」とは? 概要と計算方法
「譲渡所得」とは、不動産を売却することによって得た利益のことです。
売れたときの販売価格(譲渡価額)から、売却にかかった費用、そして自分がその物件を購入したときにかかった費用を差し引いたものが、譲渡所得となります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得=譲渡価額 −(譲渡費用+取得費用)
譲渡費用とは?
「譲渡費用」とは、売却に伴ってかかった費用のことです。たとえば、仲介手数料などの諸費用が譲渡費用にあたります。
ただし、居住中に支払ったリフォーム費用や固定資産税は、譲渡費用には含まれません。
取得費用とは?
「譲渡費用」とは、物件を売却するためにかかった費用のことです。不動産会社に支払う仲介手数料、登記費用などが該当します。
「取得費用」とは、物件を取得するためにかかった費用のことです。購入代金はもちろん、仲介手数料などの諸費用、そして「減価償却費」もこの中に含まれます。
「減価償却費」とは、建物や設備が経年によって古くなり減少した価値を、経費として計上したもの。
土地は経年によって価値が変化することがないため、減価償却の対象にはなりません。
RC造マンションの減価償却費は、以下の計算式で求めることができます。
RC造マンション(非業務用)の減価償却費の計算方法
減価償却費=建物の取得価額×0.9×0.015×経過年数
譲渡所得にかかる税金の税率は?
譲渡所得にかかる所得税・住民税の税率は、物件を所有していた期間によって変わります。
分かれ目は5年以内/5年超です。
所有期間が5年以内(短期譲渡所得)
39%(所得税30%・住民税9%)
所有期間が5年超(長期譲渡取得)
20%(所得税15%・住民税5%)
課税額を実際に計算してみよう
例題をもとに、実際に譲渡所得や減価償却を算出し、課税額を計算してみましょう。
例題
4,000万円(建物2,000万円・土地2,000万円)の新築マンションを購入した。諸費用は200万円かかった。
10年後、このマンションを4,500万円で売却した。このときの諸費用は150万円だった。この場合、所得税・住民税はいくら課税されるか?
マンションの減価償却は、2,000万円×0.9×0.015×10年=270万円。
よって、築10年時点の建物価格は、2,000万円-270万円=1,730万円。
マンションの譲渡費用は、150万円。
取得費用は、建物1,730万円+土地2,000万円+諸費用200万円=3,930万円。
よって、譲渡所得は、4,500万円-(150万円+3,930万円)=420万円。
購入後5年超の年数が経過してからの売却なので、「長期譲渡所得」に該当します。
したがって所得税率は15%。ここに復興特別税2.1%を上乗せすると、15.315%。
所得税・復興特別税: 420万円×15.315%=64万3,230円
住民税率は5%なので、
住民税:420万円×5%=21万円
合計で、課税金額は85万3,230円となります。
※本内容は机上概算です。実際はさまざまな要因から異なる金額となる可能性があります。個別具体的な課税額については、税務署等にご確認ください。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
さて、ここからは軽減措置について解説していきましょう。
10年以上所有していたマイホームを売却する場合は、軽減税率が適用されます。
譲渡所得のうち6,000万円以下の部分
14%(所得税10%・住民税4%)
譲渡所得のうち6,000万円を超える部分
20%(所得税15%・住民税5%)
譲渡所得が6,000万円を超えることはめったにないため、基本的に「所有期間が10年を超える場合、譲渡所得にかかる所得税・住民税は14%」と覚えておけば問題ありません。
所得税額が安くなるのにともなって、復興特別税の金額も安くなります。
(復興特別税は「所得税に0.21%上乗せ」という形で課税されるため)
ただし、この軽減税率が適用されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
マイホームを売ったときの軽減税率の要件
- 売却した年の1月1日時点で、10年を超えて所有していること
- 前年・前々年とこの特例を受けていないこと
- 買い換え特例や繰り越し控除の特例など、他の特例をいっしょに受けていないこと
- 親子や夫婦など、特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
- (以前住んでいたが、現在は住んでいない家を売る場合)住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること
参照:国税庁 マイホームを売ったときの軽減税率の特例(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm)
3,000万円の特別控除の特例
そもそもマイホームの売却の場合、譲渡所得が3,000万円を超えない限り税金はかかりません。
譲渡所得が3,000万円を超えることはめったにないため、実際には多くの人がこの特例によって所得税・住民税の支払いを免除されることになります。
3,000万円の特別控除の要件
- 自身の居住用物件であること
- 前年・前々年に、この特別控除や買い換え特例、繰り越し控除の特例を受けていないこと
- 収用等による特別控除など、他の特例をいっしょに受けていないこと
- 以前に住んでいたが、いまは住んでいない家を売る場合、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること
- 親子や夫婦など、特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
参照:国税庁 マイホームを売ったときの特例(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm)
注意点は、この「3,000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」との併用はできないということです。つまり、この特例を受けると、新居を購入する際に住宅ローン減税が使えなくなってしまうデメリットがあります。
譲渡所得が少額である場合、あえて特別控除を受けずに新居の購入に住宅ローン減税を使う方がお得になる場合もあります。
まずは4章の計算方法で、譲渡所得によって課税される所得税・住民税を算出し、10年間で受けられる住宅ローン減税の総額と比較してみましょう。
関連記事:住宅ローン控除とは?
住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、リフォームしたりした場合に適用になる減税制度。一定の条件を満たすことにより、住宅ローンの年末残高の0.7%が10年間ないし13年間、所得税と住民税から控除されます。
買い替え特例
住宅の買い換えをする際は、新居が売却したマンションの価格より高い場合には譲渡利益に対する課税を、次回売却するときまで繰り延べることが可能です。
ポイントは、課税を免れるわけではなく「先送りができる制度」ということです。
買い換え特例の要件
- 売却する家に、その年の1月1日時点で10年を超えて居住していること
- 売却価格が1億円以下であること
- 新居の土地面積が500平米以下、床面積が50平米以上であること
- 新居は築25年以内であるか、新耐震基準に適合していること
- もとの家の売却の前年〜翌年の間に、新居を購入すること
参照:国税庁 特定のマイホームを買い換えたときの特例(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm)
この特例を受けた場合、課税対象となる譲渡所得は、買い換えによって得た利益です。
つまり「売却価格と、新居の購入価格の差額」を基礎とし、売買にかかった諸費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。
とはいえ実際には、課税自体が免除される「3,000万円特別控除」を使われる方が多いでしょう。
買い換え特例も(3,000万円特別控除と同様に)住宅ローン減税との併用はできませんので、「住宅ローン減税を利用するために3,000万円特別控除をあえて受けないことにした」という方にもマッチしません。
この特例が検討されるケースは、もとの家を親族に売却するなど、実際にはやや限定的になります。
相続物件の取得費加算特例
相続した物件は、いわば無償で手に入れたことになるため、売却代金がまるまる譲渡所得として計上されると考えやすいのですが、実際はそうではありません。
相続によって亡くなった方(被相続人)の取得費用も引き継ぐことになるため、当時の購入価格をもとに損益を計上します。
所有期間についても、被相続人がその物件を取得した日からカウントされます。
もし30年前に3,000万円で購入した物件を相続した場合、取得費用は「3,000万円から30年分の減価償却をした価額」となります。
所有期間は、(相続が発生した時期に関わらず)30年となります。たとえ相続して間もなくても、30年間所有し続けていたものと見なされるのです。
このように、引き継いだ取得費用を計上して、なお売却益がみとめられた場合は、所得税・住民税が課税されます。
「相続税もとられたのに、さらに所得税もとられるの?」と思う人もいるかもしれません。
そこで政府は、相続物件を売却したタイミングが、相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月間)から3年以内であった場合には、納めた相続税額の一部を取得費用として計上できる、という軽減措置を用意しています。
売却で損失が出た場合は?
自宅マンションを売却して損失が出た場合の救済措置として、「住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が用意されています。
この特例によって、売った年の所得より譲渡損失が大きい場合は、その他所得と相殺して(損益通算)所得税や住民税を減らすことが可能になります。
控除しきれなかった分は、翌年以降3年間にわたって所得税と住民税から控除できます。
譲渡損失の繰越控除の要件
- 売った年の1月1日時点で5年を超えて所有していること
- 売却の時点で住宅ローンが残っており、その残額が売却価格を超えていること
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に売ったものでないこと
- 年間所得が3,000万円以下であること
参照:国税庁 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm)
上記を満たす場合、譲渡損失またはローンの残債、いずれか少ない方と同額が年間所得から控除され、所得税・住民税が安くなります。
譲渡損失の計算方法
売却価格 − (取得費用+売却費用)
実際に例をあげて、計算してみましょう。
例題
取得費用4,000万円のマンションに10年住んだあと、2,000万円で売却した。このときの売却費用は70万円。ローンの支払いは、残り3,000万円。
この場合、譲渡損失の繰越控除により所得税・住民税はいくらになるか?
なお、年間所得は600万円とする。
譲渡損失は、2,000万円-(4,000万円+70万円)=▲2,070万円。
ローンの残債は、2,000万円-3,000万円=▲1,000万円。
上記の計算から、ローンの残債の方が少ないことがわかるので、こちらを年間所得から差し引きます。
年間所得は600万円なので、この年の所得は600万円-1,000万円=▲400万円となり、所得税・住民税は課税されません。
実務では、会社員の所得税・住民税は給与から源泉徴収されるため、払いすぎた分は年末調整によって還付される形になります。
※本内容は机上概算です。実際はさまざまな要因から異なる金額となる可能性があります。個別具体的な課税額については、税務署等にご確認ください。
おわりに
ご自身の状況によって、税率が軽減される場合とそうでない場合では納税額に違いがあるなど、多少複雑に感じられる方も多いかもしれません。
マンションを売りたいと思ったときは、税金の計算や書類作成も含めた不動産売却を得意とする不動産会社に依頼することをおすすめします。
ひかリノベでは、自宅の売買サポートも行っております。「税金がいくら掛かるのか?」「どの軽減措置を利用するのが一番ムダがないか?」減税の特例との兼ね合いも含めてご案内いたします。自宅の売却をお考えの方は、売却のご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。