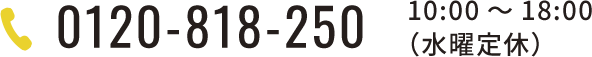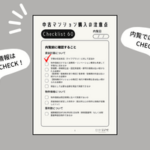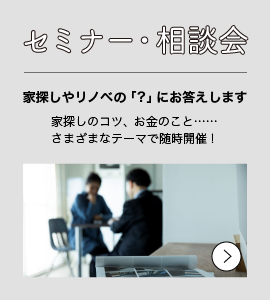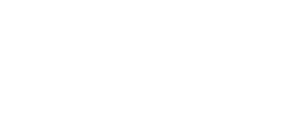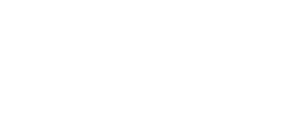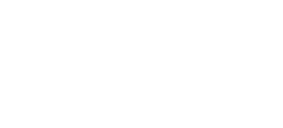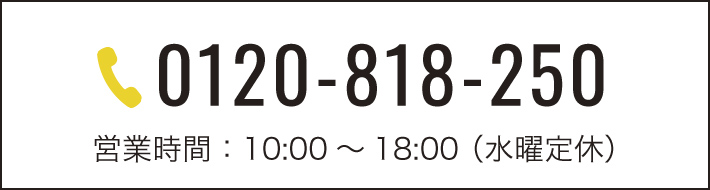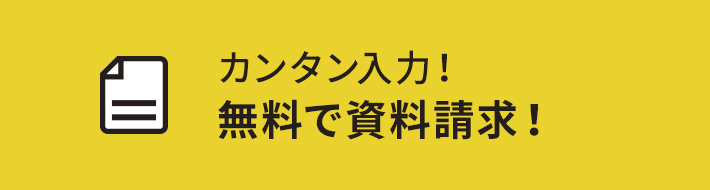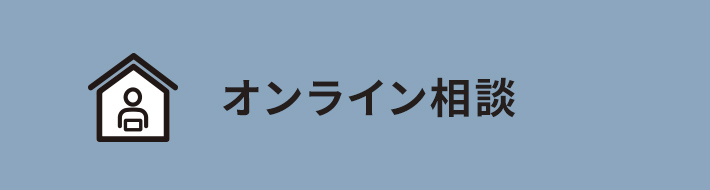出産や子育ては、マイホーム購入の大きな動機のひとつです。
夫婦共働きが当たり前の今、子育ては家族以外のサポートがもはや必須に。行政にとっても、子育て世帯の支援は大きな課題で、力を入れる自治体も増えています。
それだけに、子育て支援が手厚い地域で暮らしたい人も多いはず。
いま「子育てしやすい街」はどこなのか、日経xwoman・日本経済新聞社「共働き子育てしやすい街ランキング」(2024/12/13発表)から考えてみましょう。
目次
「共働き子育てしやすい街ランキング」1位は神戸市
「共働き子育てしやすい街ランキング」とは、日経xwomanと日本経済新聞が毎年行っているランキングです。
共働き世帯の出産・育児を支援する施策について独自の視点で調べ、それをランキング形式で評価。2015年から開始して、今年で10回目となります。
2024年は首都圏・中京圏・関西圏の主要市区と全国の政令指定都市、県庁所在地、人口20万人以上の都市の計180自治体を対象に調査を実施。43の評価項目を100点満点で採点し、「共働き世帯にとって子育てしやすいか」をランキングしました。本年は新たな評価項目として「保育園無償化への取り組み」や「保育士の配置基準」、「自治体職員の女性管理職割合」などが加わっています。
2024年の総合編1位は兵庫県神戸市(82点)。
2位は、昨年も2位の栃木県宇都宮市(79点)。
3位は東京都板橋区・豊島区・福生市・千葉県松戸市(77点)の4都市が同着です。
総合編1位~8位
共働き子育てしやすい街ランキング2024の総合編ベスト8は以下の通りです。
|
順位 |
自治体名 |
点数 |
|
1位 |
神戸市(兵庫県) |
82点 |
|
2位 |
宇都宮市(栃木県) |
79点 |
|
3位 |
板橋区(東京都) |
77点 |
|
7位 |
北九州市(福岡県) |
75点 |
|
8位 |
札幌市(北海道) |
73点 |
出典:日経xwoman・日本経済新聞社:2024年版「共働き子育てしやすい街ランキング」
1位となった神戸市は、昨年4位。西日本で初めての1位になりました。
2位の宇都宮市は昨年に続いて2年連続の2位です。
3位の松戸市は、昨年1位、一昨年2位と安定して高い評価を得ています。
ベスト8の11自治体のうち、半数に迫る5自治体が東京以外からランクインしている点も特徴的です。昨年に続いて、地方都市が多くランクインする結果となっています。
総合編 12位~19位
|
順位 |
自治体名 |
点数 |
|
12位 |
新宿区(東京都) |
72点 |
|
15位 |
市川市(千葉県) |
71点 |
|
19位 |
荒川区(東京都) |
70点 |
出典:日経xwoman・日本経済新聞社:2024年版「共働き子育てしやすい街ランキング」
昨年上位にランクインした東京23区の自治体が、今年も高順位をキープしています。
地方都市では、15位の松阪市、19位の奈良市・福岡市・福島市が昨年に引き続き高い評価を獲得しています。
子育てしやすい街ランキング上位の街の取り組み
上位にランクインした自治体では、具体的にどのような子育ての取り組みを行っているのでしょうか。ここでは3位までにランクインした兵庫県神戸市、栃木県宇都宮市、東京都板橋区・豊島区・福生市、千葉県松戸市が行っている、子育ての取り組みについて紹介していきます。
神戸市(兵庫県)の取り組み
神戸市は「自治体のダイバーシティ」の分野で高評価を得ました。市内2か所に授乳室完備で、月8回まで無料の一時保育が利用できるコワーキングスペースを設置。さらに県と共同で、女性の登用や男性育休推進に取り組んでいる企業を支援しています。市役所内のダイバーシティの取り組みも進み、23年度の男性職員の育休取得率は83.3%、課長職以上の管理職の女性比率は24.7%と、いずれも回答自治体の平均より高い結果となっています。
子育て支援では「保育の質の向上」に力を入れており、認可保育所の園庭保有率は97.7%。市内24か所に病児・病後保育施設を用意しており、全165名の受け入れが可能。学童保育は小6までの希望者全員が利用可能で、児童一人当たりの面積は1.98㎡と、厚生労働省の指針を上回る基準で運営されています。
宇都宮市(栃木県)の取り組み
宇都宮市では、保育インフラの整備で高い評価を得ています。保育園への送迎負担軽減のため、JR宇都宮駅近くに保育士添乗の送迎バスのステーションを用意。病児保育施設でも、保護者にかわって送迎をおこなうサービスを展開しています。また、塾や習い事への送迎用に、市の補助を受けたタクシー会社によって子供だけで利用可能なタクシーが運行されています。
妊娠・出産、子育てにかかる金銭的な支援も充実しており、第二子以降の保育料が無償。市独自の不妊治療助成制度があり、保険適用分を含む自己負担額のうち最大45万円が助成しされます。
こうした取り組みの成果か、移住に関する問い合わせが「3年前の10倍となっている」そう。通勤圏内ということもあり、「首都圏の子育て世代からの問い合わせが多い」と、日経クロスウーマンの取材に対して市の担当者が語っています。
板橋区・豊島区・福生市(東京都)の取り組み
東京の3都市では、都の施策によって第二子(0~2歳)の保育料が無料。
板橋区は、利便性の高いサービスが充実しています。
区内のほぼすべての認可保育所や公立小学校、区立学童保育で保護者との連絡が可能なICTシステムを導入。認可保育所では、紙おむつの定額制サービスを実施。また、すべての区立学童保育で、夏休みなどの長期のお休み中に昼食を提供しています。
豊島区は、学童保育の質の向上に力を入れています。
区内の全ての認可保育園に看護師を配置し、病児保育に対応。また全ての学童保育で夏休みなどに昼食を提供しています。首長部局の女性管理職比率が25.3%と高く、区内の民間企業にたいしても「豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度」を用意するなど、ダイバーシティへの取り組みでも高評価。
このような取り組みの結果、板橋区と豊島区では、隠れ待機児童の数が減少しています。
福生市では、小学校まで続く支援が特長的です。
市内の小学校7校中6校で、学童保育と放課後子供教室を同一校内で行っています。学童保育には小学6年生まで入所でき、市内18か所中3か所の施設で平日夜に夕食を提供しています。幼児保育に関しても、市内の保育所などすべての園で医療的ケア児の受入れが可能に。また保育士確保のため、保育士が優先的に賃貸住宅に入居できる施策を用意しています。
松戸市(千葉県)の取り組み
昨年1位の千葉県松戸市は、保育体制の強化で実績をあげています。公立保育所の保育士の配置を1~2歳児クラスでは児童5人に対し1人、4~5歳児クラスでは児童20人に対し1人と、国の基準を上回る数の保育士を配置。医療的ケア児や障がい児の入所調整を通常よりも先行し、24年4月には、実際に申し込みがあった19人全員を受け入れました。
出産まわりのサポートでも、妊娠36週以降に使える「妊産婦タクシー利用料補助金」の利用条件や回数を拡大するなど、独自の支援を用意。
学童保育では、市内45か所すべてで長期休暇中の昼食提供をおこなっています。
子育てしやすい街の指標とは?
「子育てしやすい街」とは、どのような指標に基づいて評価されるのでしょうか。
本年のランキング調査では、出産直後の母子をサポートする産後ケアへの取り組みや、保育料の無償化、ITC導入による手続きの効率化などが評価項目に追加。また、昨年に引き続き「自治体のダイバーシティ推進の取り組み」が注目指標と位置づけられており、「自治体の首長部局に勤務する正規職員における、管理職(課長相当職以上)に占める女性割合」も評価項目に追加されています。
保育の現状と今後
予想をはるかに上回るペースで加速する日本の少子化。未就学児の数が「増えた」と回答したのはわずか2自治体のみで、調査に回答した自治体のほとんどが「未就学児の数が減少している」と回答しています。
また、東京と東京以外の地域とで、保育所整備に関する自治体が抱える課題に違いがあることも見えてきました。
東京都内の41自治体では、保育所整備における課題として「将来の需要予測の把握が難しい」と回答した自治体が78%で最多。続いて「保育所の定員割れ」が課題と回答したのは75.6%という結果に。
一方で、東京都を除く114自治体では、「保育士の確保」が課題という自治体が最も多く、64.9%に上っています。
このように、保育需要の地域差だけでなく、東京以外では保育士確保も大きな課題となっています。東京をはじめとする大都市で保育士の待遇改善が進んだ結果、「地方から保育士が流出している」ことが一因となっている……という見方もあります。
まとめ
これまでの「子育てしやすい街」は、保育所の数や定員、経済的な支援策の有無や支給される金額など、わかりやすい“数字”で評価されてきたといえます。もちろん、そういった数字は今でも大事ではありますが、共働き世帯が増える中、大人(親)の働きやすさもますます重要になりつつあります。
そしてこれからは、働くことと子どもを育てることが、より密接な関係を持つようになるでしょう。働く場所も、子育てしやすいかどうかがひとつの決め手になるかもしれません。
今回は日経xwoman・日本経済新聞「共働き子育てしやすい街ランキング2024」をもとに、ベスト19までのランキングと審査分野、上位6自治体の子育てに関する取り組みについて紹介しました。
住みたい街と働きたい街、双方の視点から街や住まいを選ぶことが、これからの子育て世帯にとって大きな意味を持つはずです。
住みたい街が見つかったら、ぜひ当社ひかリノベにご相談ください。住宅リノベーションのひかリノベでは、物件探しからリノベーション設計・施工、資金計画までワンストップであなたとご家族のお住まいづくりをサポートいたします。